 “ポケッタブルラジオ”
“ポケッタブルラジオ”さて、東京通信工業(ソニーの前身、以下東通工)のトランジスタラジオも、いろいろなモデルが出てきた。たとえば1956年の暮れにできたTR-81は、 NHKから辺地(へんち)の学校用ラジオとしての指定を受け、全国200ヵ所分の注文をもらった。このラジオは、一般の販売店では売られなかったが、民生用として画期的な商品の企画が、その前の月にたてられていた。その商品こそ、当時世界で一番小さいトランジスタラジオとなった“ポケッタブルラジオ” 「TR-63」である。発売予定は、翌年の3月と決まった。
TR- 63型は、これまで世界最小のトランジスタラジオと言われ、東通工が世界初という栄誉を譲ってしまった米リージェンシー社のTR-1型ラジオ(4石で、 127×76×33mm)に対し、112×71×32mmと小さく、6石のため感度、出力とも優れており、消費電力も半分以下ということで、発売早々から評判になった。 価格は、1万3800円で、これはちょうど、その当時のサラリーマンの1ヵ月の平均給与に相当する額であった。
TR-63が世に出た当時、小さくて、ポケットに入るようなラジオは、アメリカではポケットラジオという名称で呼ばれていた。「ポケッタブル(ラジオ)」というと、今では耳慣れた言葉だが、実はこの言葉をキャッチフレーズに使ったのはソニーが初めてだった。ポータブルより一段と小さくなったことを強調するために「ポケッタブルラジオ」というキャッチフレーズを考え出したのである。ところがこのTR-63、当時の既製のワイシャツのポケットに入れようとしても入らない。残念なことに、若干ラジオのほうが大きかったのだ。これでは、せっかくのキャッチフレーズが泣いてしまう。それならと、専務の盛田がちょっとした細工を考え出した。ワイシャツのポケットを少しばかり大きくすれば、何の問題もない。そこで、普通のワイシャツのポケットより、やや大きめのポケットを付けた特製のワイシャツを用意して、セールスマンに着用させ、売り歩かせることにしたのだ。
初めてのポケッタブルラジオに対する人々の期待の強さは、このTR-63の1号機と称するものが、50台も世に出たことで分かる。1号機というのは文字どおり1台だが、何としても1号機を手に入れたいという、熱心な東通工ファンの願いをかなえるために、1号機と称されるものが50台も作られるという結果になってしまったのだ。
TR-63で忘れてはならないことが、もうひとつある。それは、この機種がトランジスタラジオの、本格的輸出1号機の任を担っていたことである。輸出価格は、39.95ドル。これは大成功で、この年の暮れには輸出が間に合わなくなり、日航機をチャーターしてアメリカに大量空輸するほどであった。このように、東通工製のトランジスタラジオを順調に輸出できるようになったのは、この年の8月に盛田が渡米して、米国で1、2位に数えられる電気機器販売会社のアグロッド社とソニーラジオ、ベビーコーダー、補聴器などの東通工製品の長期取扱契約を結んだことが大きく貢献している。
 点滅されるネオンは縦に100段の超大型。
点滅されるネオンは縦に100段の超大型。アグロッド社とは、むろん『SONY』の商標を使うことを前提に契約をした。これは、以前から盛田が固守したことであり、また、たいへん意義の深いことだったのだ。日本のほとんどのラジオメーカーは、その製品を輸出する際、アメリカのメーカー名を付けて売っているというのが実情であった。それは、当時日本製品の中で一流品としてアメリカでそのまま通用しているのは、カメラのNikonとCanonだけという状態で、それ以外の日本製品は、安かろう悪かろうの代名詞のように言われていたからだ。そんなアメリカの風潮を逆手に取って、堂々と自社のブランド名で勝負を賭けたのは、何としても『SONY』の愛称で、世界的な商品としての評価を得たい、得ることができるに違いないという、東通工の自信の表れにほかならなかった。
ブランド名といえば、この年(1957年)の暮れに、もうひとつめでたいニュースがあった。東京は銀座の数寄屋橋にソニーの広告ネオンを出したことだ。
1955年に、東通工製品に『SONY』のブランド名を付けるようになってから、次第にソニーの名も世の中に浸透していってはいたが、社長の井深たちは「もっと、名を知らしめたい。広告したい」という気持ちを常に持っていた。そこで「ネオンを作ろうじゃないか」という話が出てきた。どうせ作るなら目立つ所がいい。あちこちに声をかけて探しているうちに、数寄屋橋の角地(現在のソニービルの建っている所)が借りられるという耳寄りな情報が入った。ビルは古かったが、何よりも場所がいい。連続ラジオドラマ『君の名は』(1952年にNHKが放送)で一躍有名になった数寄屋橋も、まだこの頃には残っていた。それだけに、当時日本人が一番よく知っている場所である。
場所が決まれば、次はどんなネオンにするかだ。まず、盛田が8ミリフィルムで撮影してきたニューヨークのブロードウエイにあるネオンサインを、いろいろと見て検討した。実際に煙を出して煙草をふかす有名なキャメル(タバコのメーカー)の広告や、何10万個というサイン球をつけた豪華なペプシコーラのネオン等々、どれも目を見張るものばかりである。これらに負けないものをと、日本でも一流といわれるネオンの製作会社4社にデザインを依頼した。持ち込まれたデザイン画19枚を4日がかりで審査し、決定したのが10月の20日。
これでホッとしたのも束の間、12月10日までには完成させよとの厳命だ。ところが、予定地となった数寄屋橋のビルは、戦争で傷んでおり、大規模な補強が必要である。その上、これまでこのビルの壁面を使っていた会社のネオンが付いたままで、なかなかどけてくれない。それやこれやで、話がずるずると延び延びになって、結局工期は20日しか取れないという事態になり、全くの突貫工事になってしまった。
点灯式は12月19日。この日は特に寒い日で、全員が毛布にくるまってネオンに明かりが灯されるのを待っていた。そして、午後5時1分、井深がスイッチを入れて、夜空に明るくSONYのネオンが輝いた。大きさは、9.75×10.9m。総重量2250kg、SONYの各1文字が262.5kgもあるという大規模なものだ。費用は、鉄骨の補強代と借り賃で、約2千万円かかったが、それだけのお金をかけた効果がすぐに表れた。
この年の大晦日、NHKのテレビ電波に乗って、SONYの大ネオンが日本中に映し出されるという幸運に恵まれたのだ。これは、たいへんな宣伝である。「紅白歌合戦」が終わり、その後の「行く年、来る年」という番組の中で、東京の夜景としてこのネオンがパーッと出てきた。これを見ていた井深は、「これで、元が取れた」と大喜びであった。
 TR-6の製造ライン
TR-6の製造ライントランジスタラジオの輸出が好調であったり、銀座にSONYのネオンがついたりと、東通工にとっては良いことずくめの1957年であったが、悲しいニュースもあった。
東通工の米ニューヨーク事務所代表者の山田志道(やまだ しどう)を狭心症で亡くしたのだ。山田は東通工発展の基盤をつくってくれた恩人である。井深たちは、そのあまりに早い訃報にがく然としてしまっていた。戦前から35年間もアメリカに住み、ウォール街を第二の故郷のように思っていた山田であったが、それ以上に東通工のことを愛し、積極的な協力を続けてくれていた。そんな山田に対し、恩返しのひとつもしていない。井深や盛田は胸の内で大きな後悔を感じていた。
そうはいっても、井深や盛田にその意思がなかったわけではない。米ウエスタン・エレクトリック社とトランジスタの特許契約が締結された後、山田の功績に報いたいと、夫人ともども日本へ招待することを計画し、「東京の帝国ホテルに宿を用意しました。ぜひとも日本に来て、わが社を見てください」と言って山田夫妻の来訪を待っていたのだ。しかし、この時は山田から丁重な断りがあって実現しなかった。
山田も山田の妻も、永く日本には帰っていない。井深たちからの申し出は、涙が出るほど嬉しかったに違いない。ところが、山田は東通工の内情をよく知っている。「こんな小さい会社にお金を使わせてはいけない。もっともっと尽くしてから呼んでいただこう」。そう、2人で話し合って、断ることにしたのだった。
その言葉のとおりに、山田はその後も東通工製品のアメリカでの市場開拓のために努力を重ねてくれた。米国大手のアグロッド社と販売契約を結べたのも、山田の努力のお陰であった。この契約のために渡米していた盛田に、山田は「今年こそ、ビルのできあがった東通工を見に行きますよ」、そう言って笑っていたのはほんの 2ヵ月前のことだ。
「あの時、日本に呼んでいれば……」。急逝した山田の遺族への弔問と、代表者を亡くしたニューヨーク事務所の今後の打ち合わせのため10月末に渡米した盛田は、飛行機の中で何度となく、このことを思っていた。
ニューヨークに着いて諸事を済ませた盛田は、ぶらりと街に出た。するとどうだ。東通工のトランジスタラジオが、堂々とSONYの名前を付け、それこそ一流といわれる販売店の店頭に置かれているではないか。ついこの間、売り出されたばかりというのに、この人気だ。ニューヨークの銀座ともいうべきマジソン街の「リバティ」にも置いてある。「リバティ」は、第一級のラジオ・レコード店で最高級の品しか置かない格調高い店として有名だ。むろん、これまで日本製品を扱ったことなどない。その店先で、道行く人が立ち止まっては、じっと東通工のトランジスタラジオに注目していく。あるいは「クリスマスには……」と話し合っている。こんな街の様子を見るにつけ、盛田は何とも言えない喜びを感じていた。同時にこの盛況を山田に見せてやることができないのが残念でならなかった。「TR-63が輸入されてきた時、『こんなものができる東通工は、やっぱりすごい会社だ。自分の目に狂いはなかった』と大喜びしていた」と、山田未亡人から聞かされた後だけに、一層無念さが込み上げてくるのだった。
山田と出会わなかったら、トランジスタラジオはできなかったかもしれない。それを思うと、盛田は感慨無量であった。
悲喜こもごもの1957年が終わって、新しい年を迎えた東通工では、新年早々、社名を「ソニー株式会社」と変え、新たな出発を図った。
商標と社名を一致させるかどうかは、長い間の懸案であった。1955年に、東通工製品に「SONY」のブランド名を付けてからこの日まで、すでに3年の月日が経っている。それだけ社名変更に際し、苦慮したとも言える。「創業以来10年間もかかって、業界に立派に知られるまでになった『東京通信工業』という社名を、今さらそんなわけの分からない名前に変えるとは、何事だ」と、主力銀行である三井銀行から、さっそく叱られた。社内でさえも、今回の社名変更に納得しかね、こうした意見を持っている社員が大勢いた。
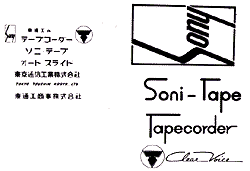 1955年頃に使用していた商標
1955年頃に使用していた商標 この点は、井深や盛田が一番苦慮したところでもあった。「東京通信工業」では海外では通用しにくい。これまでも、東通工を英語読みにして『TOKYO TELE-TECH』あるいは『TOKYO TELE-COMMUNICATION』と訳されて、発音も意味も分からないというので、いろいろ不便を感じることもあった。しかし、日本では立派に通用する名前である。しかも今やテープレコーダーの生産額においては、日本の総生産額の91%を誇っている新進気鋭の会社として、名を広めている。「SONY」という商標名が誕生してからも、常に「SONYの東通工」と言われており、ここまで営々として築いてきた名前には、それなりの誇りと郷愁を誰しもが感じている。「われわれが世界に伸びるためだ」。社の内外から「社名変更の狙いは」と聞かれて、盛田が一番先に口に出す言葉である。「そのために、わざわざソニー株式会社にしたのだ」というのが、盛田の言いたいことの核心だ。「ソニー電子工業とか、何とか電気というものを付けてみたらどうだろう」という意見もあった。しかし「断固、ソニー株式会社でいくべきだ」と盛田は、これら社名に電気に関する言葉を入れるのには猛反対であった。会長の万代順四郎(ばんだい じゅんしろう)も、社長の井深も、盛田の主張に「それで良い。それでいこう」と言ってくれた。
今日では会社名よりも商標の「SONY」のほうが人に知られるようになっているのが現状だ。「当初は、多少の混乱もあるだろう。しかし、変える前と変えた当座が問題になるのであって、しばらくすれば、そんなに問題になることもなかろう」。盛田はなりゆきを見守っていた。
東通工は、自ら10年間必死になって、しかも立派に得意先に売り込んだ社名を将来のためにかなぐり捨てた。それは、単に知名度を上げるためのみならず、盛田たちにとっては、それだけの仕事をしてみせるぞという並々ならぬ覚悟を秘めた悲願のようなものでもあったのだ。そんな盛田の思惑どおりに、「SONY」の評判は、世界中で日増しに高まっていた。
 ラジオのデザインを決める
ラジオのデザインを決めるところで、何といってもソニーのトランジスタラジオの名を高めたのが、ニューヨークで起きた盗難事件である。
米国オーディオ業界の大立物であったアグロッド社を、ソニーラジオの米国総代理店に据えて、販売網を確立したのが1957年9月。それ以後、アグロッド社は、ニューヨーク近郊のロングアイランド市に本社を置くデルモニコ・インターナショナル社の販売網を活用して、米国全土にラジオを送り込み、ソニーの名は最高級トランジスタラジオの代名詞のごとく言われ、親しまれるようになっていた。
翌年の1958年1月13日、ソニーのニューヨーク事務所開設の準備のためニューヨークに滞在していた担当者が、家に帰りラジオのスイッチを入れると、ソニーのラジオがデルモニコ社から4千個盗まれたというニュースが流れてきた。半信半疑ながら、すぐに山田志道未亡人に電話をかけて、「今ラジオで、こんなニュースが入ったが……」と言うと、山田未亡人も「確かに聞いた」と言う。
その翌日の『ニューヨークタイムズ』を見ると『日本のトランジスタラジオが4千個、デルモニコの倉庫から盗まれた』と大きな見出しで報道されている。その記事によれば、デルモニコの事務所や倉庫のある場所は、ショッピングヤードといわれる繁華街で、結構人通りの多い場所にある。その人の多い街で最も人の出盛る夕方の6時に、2階の窓を破って中へ押し入り、下のドアを開けて、堂々とトラックを横付けして4、5人の人数で盗んだということだ。しかも、その倉庫にはソニーのラジオだけでなく、ほかの会社のラジオもたくさん置いてあったのに、それには目もくれず、1梱包10個入りのソニーTR-63型400梱包だけを盗んだのである。被害総額は10万ドルであった。
 スピーカー付きで当時世界最小
スピーカー付きで当時世界最小とにかく、このニュースのお陰で、ソニーは一躍有名になった。これは、アメリカの業界はじまって以来の大泥棒だといって、その大胆な手口といい、ソニー製だけを持って行く利口さといい、新年早々からニューヨークっ子の格好の話題をさらってしまったのだ。それからしばらくの間、どこに行ってもこの話でもちきりである。「ソニーは濡れ手に粟で1銭も宣伝費をかけずに、宣伝100%の効果を挙げた」とか、「お前の所は、どうしてそんなにうまい具合に盗まれたのか、秘訣を教えろ」と、いろいろな人からからかい半分の問い合わせが相次ぎ、ニューヨーク事務所開設準備の担当者を困らせた。
泥棒に入られて喜ぶというのも、おかしな話ではあるが、この時のソニーはまさにそんな状態だ。反面、4千個の追加オーダーをこなすのに工場では非常に苦労をしたし、盗まれたラジオの製造番号を知らせたりと、東京サイドも、この盗難のため大騷ぎであった。
こうして、すっかり話題をさらったTR-63型であるが、この年の6月には、TR-63よりも一回り小型軽量になったTR-610型が発売され、輸出の決定版となった。TR-610型は、国内よりも欧米への輸出のほうが先で、斬新なデザインと性能の優秀さで大評判となり、1960年までの2年間で、日本を含む全世界に50万台が売られていったほどである。また海外の一流デパートや高級専門店では競ってTR-610を展示し、一時はプレミアム付きで取り引きされたり、アメリカから逆輸入して模造品を作るメーカーまで現れるという人気機種となり、ソニーの名を決定的に諸外国に知らしめる役割を果たしたのである。