 1981年、カラヤン氏を招いて行われた
1981年、カラヤン氏を招いて行われたこうして、中島、宮岡、土井、鶴島らがCDのハードウェアを、1982年10月の商品化に向けてまとめ上げていった。一方、大賀はCDを世界の標準規格にすべく、オランダのフィリップスと手分けして、世界中のソフトウエアメーカー、レコード会社、音楽団体の会合に出向き、内容の説明とCDの演奏を繰り返し行っていった。
しかし、CD開発当時、「黒色のお皿(アナログレコード)」に代わる「銀色に光る小さなお皿(CD)」は、ソフトウエア業界にとって魅力であると同時に脅威でもあった。中でもレコード関係者の反発は強く、ほうほうの体で逃げ帰ってくるということが何度もあった。まさに“石もて追われる”とはこのことだった。大賀たちが「次世代のオーディオの最高のメディアだから、なんとかこれを普及させましょう」と呼びかけても、「せっかくLPレコードという世界のスタンダードがあり、我々はその音に満足している。余計なことをしないでくれ」と言うのである。
CDシステムを世界標準規格とするべく、世界各地で辛抱強く説得を続ける一方、「ハードがあってもソフトがなくては使いものにならない」と、大賀はCDソフトの量産体制の整備に乗り出した。
アメリカのCBSとソニーの合弁によるレコード会社CBS・ソニーレコード(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)は、設立以来、わずか10年で国内業界トップのレコード会社に成長。直径30cmのLPレコードの量産工場を整備し、軌道に乗ったところだった。そもそも、大賀たちが、フィリップスとデジタルオーディオディスクの共同開発を決意した陰には、このCBS・ソニーの存在があり、彼らの国内レコード市場におけるシェア(市場占有率)を大いに当てにしていたのだ。
しかし、CBS・ソニーと、その親会社のアメリカのCBSレコードの幹部は、当初デジタルオーディオディスクの生産へ乗り出すのに及び腰だった。材料のビニールを溶かしてプレス作業によるLPレコードの生産と、当時最先端の半導体IC(集積回路)工場のような製造設備によるCDの生産では、かなり勝手が違い、本格的なCDソフト工場の設備を整えるためには、高額の投資を必要とする。「何から何までデジタル用の機械に入れ替える必要があるのか」というわけだ。
合弁会社である以上、CBS・ソニーの行う投資に関しては、アメリカのCBSの了承を得る必要があった。しかし、CBS・ソニーには、強みがあった。同社は当時国内のレコード業界の中でけた違いの利益率を誇っており、十分な資金を持っていた。大賀は、CDによる未来のビジネスの可能性を語るとともに、こう言ってアメリカのCBSの幹部を説得した。「あなた方には、毎年の出資に対し10割配当を行っている。CBS・ソニーが生み出した利益の一部で、CDソフト工場を建設することを認めてもらいたい」
何とか説得に成功し、静岡県大井川のほとりにある工場に、親会社であるソニーからもアメリカのCBSレコードからも1銭も出させることなく、CBS・ソニー自身の資金で、クリーンルーム(温度や湿度をコントロールするとともに、ゴミを極端に少なくした作業室)付きの本格的なCDソフト生産設備をつくった。こうして世界初のCDソフトの生産ラインは、1982年4月に稼動を始めた。
しかし、CD発売予定の10月までは、夏休み返上でソフトの生産準備を進めるなど、大変な日々が続いた。最後まで、ディスクの「反り」という品質問題が残ったのである。使えそうなあらゆる素材を調べた結果、救世主となったのは、自動車のバンパーなどに使われる「ポリカーボネート」という新素材である。ポリカーボネートを使ったディスクで商品化する決定をしたのは8月、プレス生産が軌道に乗ったのは、何と発売半月前の9月半ばであった。
1982年8月31日、ついにソニー、CBS・ソニー、オランダのフィリップス、同ポリグラムの4社共同のCDシステム発表会が大手町・経団連会館で開かれ、秋からの国内販売開始を明らかにした。当日の夕方から夜のテレビニュースと翌日の朝刊は、一斉に「オーディオの夢誘うデジタルのプレーヤー登場」「『デジタルオーディオ時代』幕開き」などと報道した。直径12cm、デジタル信号で録音されたCDは、ワンタッチで選曲、小型・軽量、録音盤の半永久的使用という、オーディオファンの夢の多くを一度に実現させ、折からのオーディオ不況を吹き飛ばすかのような新風を業界に吹き込んだ。
同年10月1日、ソニーは先陣を切って第1号機「CDP-101」を発売した。エジソンのホノグラフ発明から100年余、レコード技術は、大体四半世紀(25年)ごとに、大きな技術革新を迎えてきた。円筒方式から円盤レコードへ、電気式レコードの登場そしてLPレコードへ、モノホニックからステレオへ。そして100年目にデジタルオーディオ技術が花開いた。
 ホノグラフ(右)発明から約100年、CDプレーヤー
ホノグラフ(右)発明から約100年、CDプレーヤー この1号機をCDP-101と名付けたのは、CDの商品化を必死に推進したオーディオ事業部長の出井伸之(いでい のぶゆき)である。出井は「101」を、「0101」から名付けた。デジタルは「0と1の組み合わせ、つまり2進法の世界である。2進法では、「0101」は5を表す。出井は「5 という数字は、中級クラスの製品名を表すことが多い」と思っていたので、「これはソニーの中級機種」というメッセージを「101」に込めたのである。しかしながら、当の出井は、CDP-101の発売の日を入院先の病院のベッドの上で迎えていた。CD商品化に対する激務から、肺炎で倒れてしまったのだ。配られた新聞にCDP-101の広告を見つけ、「とうとう発売だなあ」と感慨にふけっていた。
価格は16万8000円、一般消費者向けの商品としては高額だ。しかし、盛り込まれている技術、開発期間を考えれば、商品化できたことさえ奇跡的だった。そして、追いかけるようにして発売された他社製品に比べても一番安かったのである。
しばらくして、世界各地でデモンストレーションに使われ、活躍してきたサンプル用ディスクが担当者の元に返ってきた。表面は傷だらけになっていた。しかし、プレーヤーにかけてみると……音質はもとのまま、少しも劣化せず澄んでいた。
CDP-101の発売と同時に、CBS・ソニーから世界初のCDソフト50タイトルが発売された。記念すべきCDソフトの生産第1号はビリー・ジョエルの「ニューヨーク52番街」である。
50タイトルの内訳はクラシックだけでなく、ポップスやロック、歌謡曲までそろえた。「オーディオマニアはもちろん、幅広いオーディオファンに売っていこう!」という思いの表れだ。さらに第2、第3弾の発売が続き、年末までに100タイトル余りのソフトが発売された。
思い起こすと、2年前のDAD(Digital Audio Disc)懇談会でデジタルオーディオディスクに関する3方式の評価が終了した時、ソニーとフィリップスが共同提案した方式を含む2方式が残されたはずである。しかしながら、ソニーがCDを発売した頃には、ほとんどの会社が、ソニー・フィリップス方式、通称CDシステムの採用を発表し、CDシステムは「事実上の世界統一規格」となっていたのである。練り上げたCD規格の良さ、そして2年間世界中で積極的に行ったプロモーションの成果であった。
こうしてCDは世に送り出された。ハードウエア開発では、ソニーの各部門が、事業部の壁を越えて協力し、商品化にこぎ着けた。さらに、ソニーとCBS・ソニーの両社の社員が「何とかCDを新しい時代の商品にしよう」と連携し、ハードウエアとソフトウエアの両輪をつくり上げた。「CDほど、ソニーグループ全部の持てる力をうまく使った例はないだろう」と大賀は後に語った。
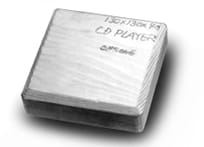 D-50のサイズの目標となった大
D-50のサイズの目標となった大1号機CDP-101の発売後、鶴島ら技術部は、「より小さなCDプレーヤー」をめざし、部品点数や消費電力を減らしたり、関係部署と連携しながら“1チップ LSI(半導体大規模集積回路)”を開発したり、光学ピックアップを小型・薄型化するなど、必死に改良を続けていた。オーディオ事業部も、CDプレーヤーのコストダウンを進めた。まず、5万円台のCDプレーヤーをつくろうという目標を先に設定した。それを実現する光学ピックアップのコストや半導体のコストを逆算してはじき出し、「こういう価格でこういうものをつくってください」と半導体や光デバイスなど関係部署に頼んで回る。始めは無理、無理と言われてしまったが、それでもデバイス担当部門が頑張ってくれた。そして、低コストで小さい半導体、光学ピックアップをつくる実力が徐々に社内に育っていった。 1983年秋には、CDP-101の10分の1のメカデッキ(演奏機構部)をつくる実力が培われるようになり、やがてCDをさらに飛躍させるモデルが登場したのである。それは、当初から大きな期待がかかっていたモデルであった。
1983年に入ると、他社からも次々にCDプレーヤーが発売され、CDソフトも年末には約1000タイトルが店頭に並ぶようになり、CDP-101も発売後しばらくはよく売れた。しかし、次第にその勢いも失われ、その後CD市場は停滞ともいえる状態が1年ほど続いていたのだ。
この頃CDシステムを購入したのは、やはり音質に非常にこだわるクラシックやジャズファン、いわばハイファイマニア層が中心で、多くの人は、まだ馴染みのあるLPを愛好している状態だった。マーケットは飽和状態、折からのオーディオ不況も依然として打破できないままだった。
「これでCDプレーヤーをやってみてくれ」と、ゼネラルオーディオ事業部長の大曽根幸三(おおそね こうぞう)は、13.4cm四方の正方形で厚さが約4cm、CDソフトのジャケット4枚分の厚さの木型(木片を加工したもの)を部下に示した。「中にバッタを入れようがセミを入れようが構わない。とにかく音が出るようにしてくれ」。大曽根の言葉に、居合わせた皆は思わず笑ってしまった。
大曽根の示す目標のハードルは、どれも「えっ?」と耳を疑いたくなるほど厳しく高いのだが、いつもこんな調子でユーモアたっぷりで、悲壮感が生まれない。また、明確な目標設定に木型を使うのも大曽根流である。「これくらいか」と手に取って確かめられる。そして、木型は使い手の気持ちを代弁するのだ。「技術的にまとめていくとどの大きさにできるか、じゃ駄目だ。この大きさこそ、皆が喜んで使う製品となるのだから」。大曽根の指揮の下、小型・薄型のCD プレーヤー実現に向け、総力が結集されたのである。
また、価格に関しては、CDの本格的普及をめざそうという当時会長の盛田が、「5万円を切る価格でいこう。最初は赤字でもきっと後で儲かるはずだ」と、方針を出した。1号機の16万8000円に比べて3分の1である。実のところ、5万円という価格はまったくの赤字で、原価率200%という数字がはじき出されていた。
 ポータブルCDプレーヤー「D-50」
ポータブルCDプレーヤー「D-50」CD発売2周年の1984年11月に「D-50」は発売された。4万9800円という画期的な価格だけでなく、CDジャケット4枚分の厚さながら、リモコンとリピート演奏機能以外、何らCDP-101の機能と変わらない。このことが、世の中にセンセーションを与えた。難しい技術を詰め込んだCDプレーヤーが5万円を切って売り出されたという事実に、社内の関係者自身も信じられない気がした。しかし、「盛田さんが決めたこの価格戦略が、その後のCDビジネスを大きく飛躍させた」と後日になって大賀は語っている。
このD-50は、低迷した市場を予想以上に喚起する起爆剤となった。「これほど売れるとは思わなかった」と担当した当事者でさえびっくりするほどの売れ行きをみせ、原価率は1年半で改善され、黒字に転換した。このD-50によってCDの新しいマーケットが開拓された。各社のCDプレーヤーの価格が下がり、ソフトも一斉に売り出され、業界全体のCDビジネスも本格的に立ち上がった。
ちなみに、D-50の流れを汲んでその後商品化された小型ポータブルタイプのCDプレーヤーは、ウォークマンのように歩きながら音楽を楽しめるという位置付けから、「ディスクマン」とネーミングされ、広く親しまれている。
CDビジネス、そしてソニーのオーディオビジネスはこうして再活性化されていった。これには、1983年に転籍先のアイワからオーディオ事業本部長として戻ってきた、鹿井信雄(かのい のぶお)のリーダーシップによるところも大きかった。鹿井のモノづくり、販売のポリシーは、「お客さまが店頭で指名して買っていただけるような商品づくり」だ。設計課長以下に、しきりに「お店の様子、お客さまの様子を自分の目で見てきなさい」と言うのが鹿井の口グセである。一方で、高い品質を備えながら魅力ある価格を実現すべく、徹底して設計から生産の効率化も呼びかけた。鹿井はオーディオ事業本部の風土を改革しようと努力した。時には自ら、セミナーを夜遅くまで熱心に開いた。「鹿井理論」として有名になったこうしたポリシーは、後に鹿井がビデオ事業本部長、テレビ事業本部長などを務める間にも社員に広く受け継がれていった。