東京通信工業(ソニーの前身。以下、東通工)で磁気録音機なるものをやってみようとしたきっかけは、やはり進駐軍の仕事と無関係ではない。
井深は、かねがね官庁や放送局などから与えられた仕様書によって作る製品とは別に、もっと大衆に直結した商品をやってみたいと思っていた。しかし、大衆商品であれば何でも良いというものでもない。ラジオは、いろんな会社ですでに手がけている。盛田は盛田で、営業的な観点から、NHK以外にも販路を広げることができる商品はないかと考えていた。そんな矢先、2人が目を付けたのがワイヤーレコーダーであった。
 創業当時の社内風景
創業当時の社内風景思い付いたらすぐやるのが東通工。さっそく研究を始めた。ワイヤーレコーダー本体は、日本電気の多田正信(ただまさのぶ・後にソニー取締役)が「こういうものがあるよ」と、戦時中、陸軍で使っていたものをどこからか手に入れて持ってきてくれた。それをバラバラに分解し、記録・再生の原理や構造などを調べた。同じ頃、盛田がアメリカ人の友人を通してステンレスのワイヤーを使ったウエブスター社のワイヤーレコーダーのキットを入手した。これはヘッドが付いていて、リールでワイヤーを巻き取るという至極簡単なものであったが、これに木原信敏(きはら のぶとし)がアンプを付けて組み立て、録音できるものに作り上げた。この機械で初めて録音したのは、水泳の古橋広之進選手が、ロサンゼルスで開催された全米水上選手権大会で世界新記録を出したというNHKの海外ニュースラジオ放送であった。
ところで、木原は井深が東京通信研究所(東通工の前身)時代に、早稲田大学専門部機械科で電気のことを教えていた学生の一人だった。木原は卒業を前に、大学の掲示板に貼ってある求人広告を見ていた。その貼り紙の1枚に"人を求む 東京通信工業 井深大"と書いてある。「ああ、あの井深さんが会社を持っているのか」
 忙しさの中にも息抜きが必要
忙しさの中にも息抜きが必要冷やかし半分、遊び半分で木原は東通工にやって来た。当時は、入社試験といっても面接だけだ。木原が持ってきた履歴書の特技の欄には"短波受信機作れます。5球スーパー作れます。ハイファイアンプ作れます"と電気のことばかり書いてある。これを見た面接官の樋口は「何だ、あんた。機械を出ているのに何ですか……電気ができるなんて変な人ですねえ」。
この冷やかし半分で来た変な人間が、すっかり東通工に居つき、ワイヤーレコーダーを手がけることになったのだった。
ワイヤーレコーダーでひと頑張りしていた頃、紙テープで音が出る機械のことを聞いた。井深や盛田は、その頃仕事の関係で進駐軍のいるNHKの放送会館にしょっちゅう出入りしていて、ある時CIE(GHQ内の民間情報教育局)の人からそのテープレコーダーを見せてもらった。実際に音を聴くと、ワイヤーレコーダーとは比較にならないくらい音が良い。
「これだよ、我々のやるものは。これは、これからの商品だ。テープでやってみよう」
この時、すでに井深の頭からワイヤーレコーダーのことは吹っ飛んでいた。
テープの音を聴いてしまった井深や盛田は、どんなことがあってもテープレコーダーをやりたいと一大決心をしている。何とか無理を言って進駐軍の将校にテープレコーダーを会社まで持って来てもらった。それは、まず社内の者にもこの音を聴かせてやりたいという気持ちのほかに、音を聴いてもらって、経理担当者を説得する必要が井深と盛田にはあったのだ。
経理の太刀川(正三郎、当時取締役)が仕事していると、井深と盛田が囲いの向こう側からやって来た。「実は……、テープレコーダーというものをやりたいのだが、30万円ばかり出してくれないか」「……」「使っても良いか……」。井深たちは、いとも簡単に言うが30万円は大きい、経理を預かる太刀川や長谷川(純一、当時取締役)にしてみれば、おいそれと出せる金額ではない。
テープレコーダーの音を聴かせ、さらに会社の近くの料理屋に2人を招き、「これは絶対に将来性がある。やろうじゃないか」と再度説得し、やっと了解してもらった。
 創立当時の役員
創立当時の役員さて、テープレコーダーは、アメリカでもできたばかりの貴重品である。何しろ、その当時日本でテープレコーダーをやろうと考えている者など誰もいないし、参考書は何もない。唯一あったのが丹羽保次郎氏が著した『音響工学』という本だ。それもたった2行、『1936年に、ドイツのAEG社によってプラスチックに磁気材料を塗布したテープレコーダーが発明された』という記述があるだけで、何とも心もとない限りである。テープのベースを何にするか、磁気材料にはどういうものが適しているのか、何もかもが手探りである。
とにかく粉は磁性があればよいというのでまず最初に、東京工業大学の加藤与五郎博士の発明したOPマグネットでやってみることにした。井深が、OPマグネットの棒状になった塊を持って来てくれた。これを、木原がすり鉢でゴリゴリ1時間ぐらいすりつぶして粉にした。それをちょうど鍵盤模写電信機(独で開発されたアルファベット文字電送機=ヘルシュライバー)に使っていた分厚い幅8mmの紙があったので、それに塗ってみることにした。「塗るといっても、何で塗ればいいんだろう」。いろいろ考えて、ご飯粒をすり潰し、それを糊にして塗ってみた。結果は、ザーザーというノイズが出るばかりで、音は出てこない。
いろいろと文献を探り、やっとたどり着いたのが蓚酸(しゅうさん)第二鉄である。これを焼くとマグネ(酸化第二鉄)ができると本に書いてある。「これだ、これだ」。木原は、すぐさまこのことを皆に伝えた。しかし、終戦すぐの頃で、そんな薬品はどこにも売っていない。「じゃあ、俺も探しに行こう」と盛田が言って、手伝ってくれることになった。すぐさま、2人は電車に乗って神田の薬品問屋街に出かけた。盛田は、こういう時の行動が非常に素早い。散々探し回って、やっと1軒だけ売っている所を見つけた。試薬ビンを2ビン買い求め、さっそく社に帰って実験だ。
乾溜(かんりゅう。この場合は、加熱して水分と炭酸ガスを取り去り酸化第二鉄を作る)するにも電気炉なんてものはない。炊事のおばさんからフライパンを借りて来て、蓚酸第二鉄の黄色い粉をしゃもじで炒る。色合いを見て、茶色くなるか黒くなるかというところまで焼いて、フライパンを水につけ反応を止める。茶色が酸化第二鉄、黒いのが四酸化鉄である。これ以上焼くと、空気中の酸素とますます結合して、金属を磨く時に使う紅殻(べんがら)になってしまう。色の頃合いを見計らって下ろすのは、木原の名人芸であった。
こうして、粉(磁性粉)ができた。
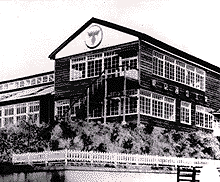 新設された"山の上工場"
新設された"山の上工場"さて粉はできたが、これを塗るのが問題だ。井深たちは、まだその頃は塗るという考えにとらわれていた。それなら塗装だ。塗装をするなら、スプレーガンだということになった。透明ラッカーに粉を溶かし、スプレーガンで、シューと吹き付ける。これでやるとほんのわずかに"音がするような気がする"程度の音が出る。しかし、スプレーガンだと紙の上にスプレーされるよりも、その周りに付くほうが多くて効率が悪い上、表面もザラザラしていて駄目だ。
この実験を行ったのが、御殿山のバラック工場の隣に新設したばかりの"山の上工場"。ここには、まだ誰も引っ越しをしていない。テープを作るのには打ってつけの---広い上に、床がまっさらできれいだった---場所である。木原は、早くテープを作りたい一心で、その床の上にテープを張り付けスプレーをかけた。いっぺんで床は真っ黒けだ。樋口から大目玉を食らってしまった。
そのうちに、井深が狸の胸毛の刷毛(はけ)が良いということを聞き込んできた。果たして、上野・松坂屋の近くの刷毛屋に行ったら、ちゃんと置いてある。大枚800円をはたいて買った。テープを室内に長く張り巡らし、刷毛を持って走りながら塗る。人間コーティングマシンだ。しかし、これもスプレーガンと大差なかった。
さらにいろいろ実験を重ねていくうちに、テープの粉は細かいほうが良いというところに行き着いた。ところが、粉を細かくする技術というのが皆目見当がつかない。その頃の新聞にある化粧品会社の"おしろい"の広告がよく出ていた。その広告には顕微鏡写真が載っていて、自分の所の"おしろい"は、こんなに細かいのだ、他の会社の"おしろい"はこんなに大きいのだと大々的に宣伝している。
「これだ! ここに行けば細かい粉を作る技術を教えてもらえるに違いない」
盛田は、紹介もなしにその化粧品会社の社長を訪ねて行った。
「実は、私どもでこんなものを作ろうとしています。"おしろい"を作る訳ではありませんので、どうか細かい"おしろい"を作る技術を公開していただけないでしょうか」
「お宅では、どのくらい細かい粉が欲しいのですか」
「3000メッシュ(メッシュ=ふるいの目の大きさを表す単位で、数字が大きいほど粉は細かい)か4000メッシュくらいの非常に細かい粉です」
これには社長も大笑いだ。
「盛田さん、それはケタが違いますよ。あなたが思っているくらいに細かい"おしろい"を作ったら、女の人が顔にはたくと、軽すぎてみんなホコリになって飛んでしまって顔に付きゃあしませんよ」
試行錯誤の連続であった。思いも寄らないような難問が、あちらこちらで井深や盛田を待ち受けていた。
磁性粉やテープのベースなど、いろいろな問題を一つひとつ片づけていき、とにかくテープを走らせてみようということになって、木原が簡単な装置を作った。78回転レコード用のプレーヤーのターンテーブルを2つ並べ、一方のターンテーブルの真ん中に3cmくらいのリールの芯のようなものを止めてテープを張り付け、もう片方にはリールを置いておく。ターンテーブルを回すと、だんだんテープが巻き取られて走ってくれる。その間にヘッドを置いて録音するという非常に原始的なものだ。テープは10mしかなく、リワインドも手で巻き戻す。「本日は晴天なり」とやっては、また一所懸命巻き戻し、「うん、聞こえるなあ」とやっていたわけだ。こうして、なんとかこれで音が出るということが分かり、東通工では本格的にテープレコーダー作りに取り組むことにした。
 テープレコーダー試作1号機
テープレコーダー試作1号機そんな折、NHKにテープレコーダーがあると聞きつけ、木原がさっそく見に行った。「はあー、機械はこんなものか」。木原には、一目見てすぐにテープレコーダーの何たるかが分かった。機械の設計図は、NHKから帰って一晩徹夜して、すぐに書き上げてしまった。翌日から、工作の人たちに手伝ってもらって機械本体の製作に取りかかり、1週間で試作機を作り上げてしまった。唯一苦労をしたのが、モーターとベルト用のゴムだ。テープレコーダーに使えるような強力なモーターが手に入らない。仕方なく、ある電気メーカーで作っていたターンテーブル用のインダクションモーター(誘導型交流モーター)を使ったが、これだと家庭の電源電圧が上がったり下がったりすると途端にスピードが変わってしまう。また、ゴムは当時天然ゴムがほとんどで、これが伸びたり切れたりで苦労の連続であった。
一番最初に木原が作った試作機は、アメリカですでに実用化されていた、"マグネコーダー"から原型を取った縦型のテープレコーダーであった。この試作1号機が1949年9月にできあがり、続いて1950年1月にG型、2月にA型の試作機が完成し、国産初のテープレコーダー誕生に向けて着々と歩を進めていった。G型は据え置き型で業務用に、A型が普及タイプということで企画されたが、A型は試作段階で製作を終え、後に発売される普及型1号機H型に引き継がれていった。こうして、製品として日本初のテープレコーダーとなったのがG型である。ちなみにG型の"G"は、ガバメント(Government)のGである。
G型を発売するにあたって、東通工では「テープコーダー(Tapecorder)」という登録商標を取った。今後、日本国内で使われるテープレコーダーすべてを、東通工の商品名である「テープコーダー」と言わせてしまおうという考えからだ。同時に東通工製のテープは「ソニ・テープ(SONI-TAPE)」と名付けられた。
 紙テープと磁性粉
紙テープと磁性粉1950年3月15日号の『毎日グラフ』で、東通工のテープレコーダーが記事と写真で紹介された。いわく"これは、最近日本で大量生産に移ろうとしている「もの言う紙」とも言うべきテープ録音機である。どこで使ってもこんな重宝なものはないが、さらに進むと、「もの言う雑誌、新聞」ができる可能性もあると製作者は言っている"。また、写真説明のひとつには"現在の蓄音機も、この機械にやがて駆逐されるかもしれない"と、テープレコーダーの未来を象徴しているかのような記述が見える。井深がテープレコーダーに目を付けてから、1年が経っていた。数々の試行錯誤、徹夜に継ぐ徹夜の研究の日々、皆の苦労がやっと報われる日が来たのである。
さて、井深や盛田はG型が完成した時、「日本で最初のテープレコーダーができたのだから、これは飛ぶように売れるに違いない。これで我が社も大儲けができる」と大喜びしていた。しかし、いざ販売を始めてみると散々である。盛田は、この機械を持って歩いて初めて気づいた。「面白い、便利だ」と皆一様に驚いてくれる。自分の声を聴いて、ゲラゲラ笑ったり、喜んだり、遊んではくれても誰もが決して買おうとは言ってくれないのだ。「面白そうだな、いっぺん使ってみるから持って来てくれ」。そう言われて盛田が持って行くと、「今から宴会があるからついて来い」と言われる。買ってほしい一心で宴会場に行くと、芸者さんやお客さんがうたう小唄を入れたり再生させられたりと、まるで太鼓持ちのようなことまでやらされる。そこまでしても、結局は買ってはくれない。
 G型テープレコーダ「GT-3」
G型テープレコーダ「GT-3」こんなはずではない。「日本で初めての画期的な商品だ。しかも、これほど便利なものを客が買わないはずがない」と思ったが、"捕らぬ狸の皮算用"であった。「良いものさえ作れば、どんどん売れるはずだ」という井深たちの当ては完全に外れた。考えてみれば、G型は当時のお金で16万円もする。それに重さが35kgもあった。当初、東通工でテープレコーダーをやろうとしたのは、大衆に直結した商品を作るためだ。しかし、結果としてできあがったものが、この大きさでこの値段では、一般のお客さまが手を出すのはとうてい難しい話であった。