Cutting Edge
光学エレメントが描く、未来への軌跡
2019年9月2日

今、世界中のフォトグラファーがその描写力を認めるソニー最高峰の交換レンズ
「G Master」。そのキーエレメントとなるのが、レンズ精度をナノレベルでコントロールした超高度非球面レンズ「XAレンズ」だ。光学メーカーとして後発だったソニーが、いかにして他社を凌ぐレンズを開発できたのか。20年間にわたる非球面レンズ開発の歴史を紐解きながら、最先端の光学エレメントの研究開発を担ってきた3人の技術者に話を訊いた。
プロフィール
-

中西 仁
ソニーイメージングプロダクツ
&ソリューションズ株式会社
デジタルイメージング本部
コア技術第1部門
エレメント設計部 -

黒田 大介
ソニーイメージングプロダクツ
&ソリューションズ株式会社
デジタルイメージング本部
コア技術第1部門
光学設計部 -

増田 敏博
ソニーグローバル
マニュファクチャリング
&オペレーションズ株式会社
レンズセンター
製造技術2部
開発当初は、すべてが暗中模索だった
──XAレンズの開発までには、さまざまな苦労があったと思いますが、まずはソニーの非球面レンズの開発は、どのようにしてはじまったのか教えてください。
中西:ソニーの非球面レンズの開発の歴史は、今から20年ぐらい前にさかのぼります。最初は、カムコーダーやデジタルスチルカメラなどに搭載される、ソニーの内製技術でしかつくることができない高精度の小さな非球面レンズの開発に着手しました。非球面レンズは径が大きくなるほど加工の難易度が高くなるため、まずは小さなレンズを高精度で加工できる技術を蓄積し、量産化できる体制を整えながら、徐々に大きなレンズへとステップアップしていきました。
黒田:当時のカムコーダーはまだHDでも4Kでもなく、カメラのイメージセンサーも解像度が低かったので、レンズに求められる性能もそれほど高くなかったんです。しかし、デジタルカメラが急速に普及し、ユーザーが求める高い解像力を実現するためには、センサーの高画素化とともにレンズの高解像化も求められました。その要求に応えるには、レンズ1枚で光学収差を効果的に補正でき、かつ小型・高性能化できる非球面レンズが設計的にも欠かせませんでした。さらに将来的にも他社製のレンズを使っていては差異化ができなくなることは明らかでしたので、非球面レンズの内製化に大きく舵を切りました。
増田:ただ、内製化に向けて舵を切ったのはいいのですが、当初は非球面レンズをつくった経験者がひとりもおらず、どうやってレンズを評価するとか以前に、まずはどうやったら非球面レンズをつくれるのか、素材から加工プロセス、それを量産化するための設備を含めて、すべてが手探りの状態でした。

20年もの歳月が結晶化した光学エレメント
──非球面レンズを量産化できるまでに、どれくらいの年月が掛かったのでしょうか?
増田:はじめて量産化できたのが開発から3年後、球面ガラスの上に樹脂で非球面をつくる「ハイブリッドレンズ」と呼ばれるものでした。ただ、最初の量産化には失敗しまして…。歩留まりが悪くて2カ月で生産がストップしました。レンズ表面に模様みたいなものが出てしまい、それを解決しようとするとレンズの商品価値が損なわれてしまうような状態で、そこから約1年かけて問題点を洗い出し、さまざまな製造やプロセスを改善することで解決しました。
この経験を踏まえて、ようやく量産が軌道に乗るのですが、現在、主流となっているガラスモールド非球面レンズに移行するまでには、実は10年の歳月を要しています。と言うのも、ガラスを溶かして成形するガラスモールドは、技術はもちろんのこと非常に大きな設備投資が必要で、他社から購入するほうが安かったんです。しかし、当時の上長たちが「多少コストが掛かっても、我々の光学技術を伸ばすべきだ」と決断し、ハイブリッドレンズの量産と並行して研究開発を続けました。
中西:そのときに我々が目標とした製造基準が、設計値からの誤差をサブミクロンレベルに抑えること。この精度でレンズを加工できる技術は、まだ世の中にも存在しませんでしたので、すべて自分たちで開発せざるを得ませんでした。それを実現するために、まず金型をサブミクロンの精度で加工する技術を開発し、成形プロセスを実現する設備のアップデートを繰り返した結果、高度非球面レンズ「AA(advanced aspherical)レンズ」にたどり着きました。そこから精度をさらに高めて現在G Masterに採用されている超高度非球面「XA(extreme aspherical)レンズ」に至るわけですが、レンズの面精度をナノレベルでコントロールできる製造技術を確立するまでには、20年近くかかりました。レンズ開発には、時間もコストもかかるので、先輩たちの先見の明と強い意志がなければ、このG Masterというブランドも誕生しなかったと思います。

綿密な技術連携が、G Masterというブランドを支える
──XAレンズの技術開発において、みなさんはそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか。
中西:私はXAレンズの設計を担当し、たとえば光学ガラス材そのものを開発したり、新たなレンズ形状を開発したり、金型開発や成型プロセス設計をしています。意外と知られていないのですが、世の中には200種類以上の光学ガラス材料が存在していて、その中でも非球面レンズに加工できる材料は限られてきます。世の中にない光学エレメントを開発することにあたり、光学ガラス材料・金型材料等の素材開発も行います。ダイヤモンドに近い特性を持つ硬度が高い材料や、硬度が非常に低く化学的に脆弱な材料でレンズ開発することがあり、材料開発から加工・成型プロセス設計まで含めると数年かかるレンズもあります。
黒田:私はG Masterなどのレンズの光学設計を担当し、どういうレンズ配置や群構成にすれば光学性能を発揮できるか、どこにXAレンズを使えば最も効果的かなど、シミュレータを使いながら限られたサイズや仕様の中でレンズ性能を最大化するのが仕事です。「こんな形状や屈折率のレンズが欲しいんだけど」と、中西さんにプロセス設計や技術を開発してもらって、新しい光学エレメントの製作を依頼することもあります。
増田:私は中西さんが設計した基本的なプロセスをもとに、量産化するための製造技術や設備を開発しています。レンズの加工プロセスはベースになるものがあり、それをカスタマイズしていくのですが、同じガラス材を同一条件で成形しても、レンズ形状が異なれば狙い通りに成形できるわけではありません。一つ一つのレンズで加工プロセスのレシピが異なり、安定的に量産できるようになるまで膨大なテストを繰り返し行います。もし、問題があれば設備そのものから見直しを図ります。量産がはじまってからでは取り返しがつかないので、設計段階から「この規格だと量産はちょっと無理」「じゃあこの設計だったらできる?」と中西さんや黒田さんと日々議論しながら、XAレンズの精度を高めています。

──世界のフォトグラファーにも描写性能を認められつつあるG Masterですが、 他社製のレンズと比べてどのようなアドバンテージを持っているのでしょうか?
中西:高い解像力と美しいぼけを最高レベルで融合させたのがG Masterです。本来、光学的に「高解像」と「美しいぼけ」は相反する性質のため、両立は非常に難しいのですが、それを実現させたキーエレメントが「XAレンズ」です。XAレンズは、設計値との誤差が極めて少ない「高面精度」と、レンズ表面が非常になめらかな「高面粗度」を実現しています。特に面粗度においては一桁ナノメートルというレベルでの平坦性を実現し、これにより非球面レンズの長年の課題だった、点光源を撮ったときに玉ねぎのような線が見える「輪線ぼけ」をなくすことに成功しています。このナノレベルの平坦性と「高面精度」の両立が、他社に真似できないアドバンテージとなります。
増田:輪線ぼけはレンズ表面に残るわずかな研削痕によって生じるのですが、この研削痕をなくすにはこれまたナノオーダーでの研削と研磨が必要で、加工機の高度な制御や操作する側のスキルやノウハウにも依存します。非球面レンズはレンズ面が複雑な形状のため、研削の難易度も格段に上がるのですが、研削するときには極力痕を付けず、研磨するときには落とせるように、工具の直径や回転ピッチなどさまざまな要素を組み合わせて、レンズ形状に誤差が生まれないように高精度に研削しています。
黒田:XAレンズを製造しはじめた頃は、φ40mmのレンズ径しか作れなかったので、レンズ設計も標準・中望遠レンズが主流でした。最近では最大径が約60mm以上のものまで作れるほど製造技術も進化し、FE 16-35mm F2.8 GMのような広角ズームレンズの設計まで可能になりました。つまりG Masterのラインナップは、光学エレメントの進化によって決まると言っても過言ではありません。

矛盾する事象を、技術によって解決する
──XAレンズを開発・製造する難しさや課題とは何でしょうか?
増田:非球面レンズの生産プロセスについて具体的にお話ししますと、まずガラス材に熱を加えてプレスし、金型の形状を転写します。その状態から徐々に冷やしていくのですが、その際にアニール処理といってプレス時にレンズ内部にたまった応力を解放していきます。この応力をうまく解放させないと、レンズが破損したり、屈折率なども変わってしまいます。その処理をした上で、光軸に偏心がないように研削してレンズ外形をつくり、さらに反射防止コーティングや外周部の光の乱反射を抑える墨塗りの工程を経て、ようやくひとつのレンズが完成します。
中西:レンズごとにガラス成分が異なるため、プレスする際の成形温度や圧力、冷却時間などの条件も変わります。考慮すべき成形のパラメーターが非常に多く、それこそ組み合わせは無数にありますので、最適なプロセスの条件を導き出すのは非常に時間がかかります。今では実験データの蓄積によって、設計シミュレーションに落とし込めるまで確立できましたが、最初は実験につぐ実験で、1つの条件を作りあげるために2〜3カ月もかかりました。
増田:ガラス材は膨張と収縮を繰り返しますので、金型を完全転写させるのはかなり難しくて、たとえば600℃以上で加熱した場合でも、たった0.1℃の違いでレンズ精度に差が出ます。収縮率が変動して形状誤差が出たり、応力が残留して屈折率にばらつきが出たり。それくらいシビアな管理が必要で、レンズの成形機に使われる温度測定機も市販のものでは要件を満たせません。温度測定機そのものから開発する場合もあり、プロセスや設備、すべての工程でさまざまな工夫を入れ込んでいます。こうした条件に適したプロセスや設備、ノウハウを持っていることで他社に対して圧倒的な性能の優位性を持つXAレンズが量産できます。
また、量産化していく過程で精度が出なかったときには、その原因を突き詰めないといけないのですが、ナノレベルとなると、もはや目で見て分かる世界ではありません。さらに非球面レンズは両面の形状が非対称であるため、熱伝導や変形のプロセスも複雑で、なぜそのような現象が起こるのかわかっていないこともあります。そこは想像力を駆使するしかありません。経験則で解決できる部分があればラッキーで、どう考えてもこれまでの現象と矛盾することが起きることも多々あります。そういうときは今までの常識を捨てないと、その先へ想像力が追いつかなくなってしまいます。

──G Masterの光学開発においても、同じような難しさや課題があるのでしょうか?
黒田:G Masterのレンズ設計で難しいのは、「高解像」と「美しいぼけ」を両立させる、わずかな設計のクライテリアを見つけ出すことです。そのためには、ぼけ味をはじめ官能的な評価をいかに定量化するかが1つのポイントです。定量的な判断ができないと我々も設計できませんので、ぼけ味を数値化できる測定機なども開発し、光学的なシミュレーションも可能にしました。これによりレンズ設計の限界値を導き出し、レンズにあわせて最適化できるようになったことが、G Masterを設計する上での大きなブレイクスルーでした。初期のシミュレーター開発には3、4年ほどかかりましたが、こうしたデータの蓄積と可視化の上で、ようやく解像とぼけの両立できるものづくりが実現できるようになりました。
G Masterはそれだけに留まらず、光学性能を高めると大きくなるレンズを、いかに小型化するか。AF速度を上げると落ちてしまうピント精度をいかに維持し、さらに向上させるか…。G Masterは、まさに矛盾する事象のかたまり。しかし、何も諦めない、何も妥協しないことがG Masterの基本哲学ですので、常に極限まで挑戦し、課題が尽きることはありません。こうした矛盾する事象を技術によって解決しようという情熱と、技術者として新しいものを生み出そうとするモチベーションがなければ、ソニーの映像技術の進化はあり得ません。
──どのような信念や目標のもとに、技術開発をしているのでしょうか。
黒田:やっぱりお客様のほうを向いて商品開発するのが、我々に課された大きな使命だと思います。技術者はともすると新しさばかりを求めがちで、お客様を忘れてしまう瞬間があります。そういう独りよがりな商品は、お客様からも「そんなのいらいよ」と言われてしまうので、そうなってしまうとお客様だけでなく、商品も自分たちも不幸です。だからこそ、本当にそれがお客様のためになるのかを常に考えるようにしています。

増田:製造事業所の役割は、あくまで製品をしっかり作って供給することに尽きます。でも、ひとりの技術者として言わせてもらうと、他社と差異化できるようなレンズをプロセスによって実現し、多くの人たちに届けられることは我々の誇りであり、モチベーションにもなっています。光学エレメントというひとつの部品であっても、そのピースが欠けてしまえば製品供給がストップしてしまいます。また、設計や組み立て、製造部門まですべてが連携してひとつの製品を作り、またG Maserというブランドを作っているので、非常に重要な責任を負っていることを、ひしひしと感じますね。
今持っている技術で、どんな次の技術をつくり出せるか。
──これから光学エレメントの技術をさらに進化・発展させていくためには、どのような人材が必要だと考えていますか。
中西:「新しいことが好きな人」が、技術者として一番ですね。いまは非球面レンズを開発していますが、この先に出てくる新しいエレメントに対しても、想像力豊かに考えてチャレンジできる人。そういう人であれば、今やっている技術はもちろんできるし、その先の将来の技術まで考えられると思います。
増田:プロセスひとつ作ることを考えても、まったく同じものがない世界。経験はもちろん大切ですが、常に新しいほうに考えられるマインドがないと先に進めません。よくみんなで言うのが、いま持っている技術で勝負するのは当たり前で、その技術を使って次どんな技術を生み出せるかが重要ですね。
黒田:光学エレメントの進化は、連続的な部分もありますが、ときには非連続的なものも求められます。これまでの常識を覆すようなものは、今まで考えもしなかったアプローチでしか生み出せません。たとえば、超望遠単焦点レンズFE 400mm F2.8 GM OSSの開発では、他社のレンズに比べて光学性能を上げながら、1Kg以上もの軽量化を達成したのですが、これまでのレンズ設計の常識から外れた思想で設計されています。ある設計者のひと言から生まれたのですが、つまり、新たなブレイクスルーを起こすには、これまでの自分を否定するぐらいの気持ちが必要で、そういったメンバーが集まり、多様な意見によってこそ進化が生まれると思います。そういう多様な意見をすぐに取り入れて商品化できる、そこがソニーの強みではないかと思いますね。
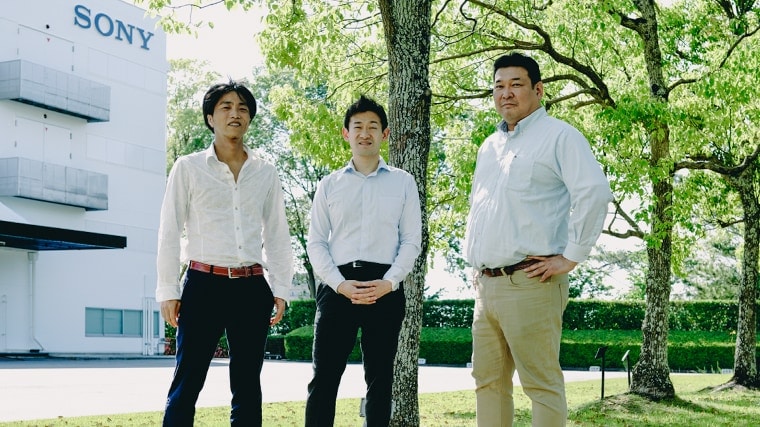
──最後に、今後の光学エレメントの研究・開発における展望などを教えてください。
黒田:世の中にないものを作り出すのが、我々技術者のミッションです。実は、10年前には「ソニーってレンズを作ってたんだ」とよく言われました。でも、ようやくG Masterを世の中に送り出すことができ、多くのフォトグラファーの方にも認知されつつあります。まずは、しっかりとお客様が望む商品を送り出すことが最優先です。その上で、これまで蓄積してきたレンズや映像技術を使って、他の事業領域へのアプローチすることで、新たな映像体験を提供することも必要だと考えています。
中西:光学エレメントもまだまだ未開拓の領域がありますが、一方で光学系を一新するような研究開発も進んでいます。具体的にはお話しできないのですが、その出口が光学エレメントとは限りません。5Gによる次世代通信やAIの進化によっても、まったく違う特性を帯びたエレメントが求められます。そのときに、必要なものを提供できる体制を整えておかないと、我々も存在価値がなくなってしまいます。だからこそ、新しい世界に対する感度を常に高めておく必要があり、未来の体験をつくりだせるような新たな光学エレメントを開発・設計・量産に関わる全メンバーが一体となって世の中に送り出していきたいと思います。




