Cutting Edge
教育における「地域格差」をなくし
「個別最適な学び」をうながすための準備は整った
2020年12月18日

VUCAという言葉に象徴されるように、コロナ禍以降の社会は、これまで以上に不確実性や曖昧性に満ちている。そんな時代を生きていくことになる子どもたちを取り巻く「学びの質」や「学びの環境」に対して、果敢に切り込もうとしているのが株式会社ソニー・グローバルエデュケーションだ。オンライン授業プラットフォームの開発に携わる酒井 英佑と、AIを活用した学びの実践研究をおこなう今川 弘章に話を訊いた。
プロフィール
-
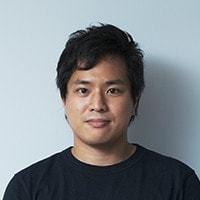
酒井 英佑
株式会社ソニー・
グローバルエデュケーション
中長期企画部 -

今川 弘章
株式会社ソニー・
グローバルエデュケーション
中長期企画部
──株式会社ソニー・グローバルエデュケーション(以下、SGED)は、どのような課題や現状認識のもとに立ち上がった会社なのでしょうか?
酒井:設立は2015年4月ですが、私が加わったのは2016年1月ですので、私が知る範囲で申し上げたいと思います。
会社設立の背景に、STEAM教育という言葉や概念が先行してあったわけではありません。あらゆる面でスピードが速くなっているのに、とりわけ日本の教育はいまだに紙とペンが重視され、どんどん教育現場が時代に置いていかれているという認識があり、それに対し「テクノロジーによってその課題を解決していこう」「教育をもっと変えていこう」という思いが設立趣旨であったと理解しています。

──ちなみにSGEDが標榜しているのは「STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics/科学・技術・工学・数学)」ですか? それとも「STEAM(STEM+Arts/リベラルアーツ、芸術)」ですか?
酒井:STEAMですね。Aは遊び心の側面もあり、とても重要な要素だと考えています。
──ソニーらしいですね。では、STEAM教育に対するSGEDならではのアプローチやフィロソフィーの特徴とは何でしょうか?
酒井:それこそ「A」を意識している点と、多様性を重視している点でしょうか。例えば主力製品である『KOOV®』は、創造力を育成するプログラミングキットです。これからの時代 は、「1+1=2」のような答えが1つに決まりきった課題だけではなく、答えがない課題に向き合う必要があります。自分たちで課題をどう定義するか、そしてそれを周りと協力しつつどう解決するか、という力が必要です。そのためには創造力や多様性が不可欠だと考えていて、そういった力を育めるコンテンツやプログラムを提供できればと思っています。
もうひとつ、我々はソニーのグループなので、楽しさの追求は大事にしています。教育というとまじめな印象がありますが、みんなで楽しみ、盛り上がりながら、型にはまらずに学んでいけるというコンセプトを大事にしています。
今川:もう1点付け加えると、ソニーのPurposeにも含まれている「感動」も大事にしています。サービスやコンテンツを考えるときにも「感動」というワードは常に念頭に置いていますね。また、創造力を育むという点では、スキルなどよりも、アティチュードといいますか、主体的に取り組む姿勢を育みたいと考えているところがSGEDの特徴ではないかと思います。

「もの」という概念の拡張とSTEAM教育
──STEMやSTEAMというくくりができたことで、新たに顕在化した利点はあるのでしょうか?
酒井:2010年代初頭にメイカーズムーブメントが登場し、誰もが手軽にものづくりができるような環境ができてきたことで、「ものづくりが教育になるのではないか」という流れが生まれたと思います。ものをつくるのは多くの学びがあることであり、STEMはものづくりに不可欠な要素ということで、フレームワークになっていったのだと想像します。
よく、「数学や歴史って何のために学ぶのですか?」ということを言う生徒がいたりしますが、それは、興味をもってもらえていなかったり、学ぶことの意義を伝えられていないという点がもったいないと思うのです。その点、STEMないしSTEAMは、ものづくりという明確なアウトプットがあることで、意義が伝えやすかったり、学ぶ意欲をもってもらいやすいという点は利点ではないでしょうか。「これを学んだらあれをつくれるようになる」ことが明示されることで、「だったら、ぼくはこういうものをつくりたい」といった具体的なイメージが浮かびやすくなるはずで、各々が主体的に学んでいくためのガイドの役割をするのではないかと思います。
今川:STEMやSTEAMという言葉は、教科間の壁を取り払うひとつのきっかけとなった言葉でもありますよね。これまでは指導や知識習得の観点から歴史なら歴史と、教科として区切られていました。それがSTEMあるいはSTEAMの登場により、複数の分野を統合的に学び、それらを活用して社会問題などに取り組んでいこう、という方向に意識が向いたのは重要なことだと思います。

酒井:一昔前と比べて、「もの」という概念は随分広がったのではと思います。形があるものだけが「もの」ではなくて、例えばSNSや動画配信サービスなど、画面の中で完結しているサービスやシステムも「もの」だと私は思っています。これらのサービスはパソコンがあればつくれてしまうので、工場がないと何もつくれなかった時代よりも、ものづくりは我々の生活に身近な存在となっていると思います。そのつくり方を学ぶことはこれから生きていく上で重要だと思います。
必要なのは「完結型」のプラットフォーム
──SGEDがいま開発している「オンライン授業プラットフォーム」について教えてください。
酒井:ある学習塾さんにインタビューをしたとき、東京と地方とではあらゆる面で教育格差があり、なかなかそのギャップを埋めることができないという課題認識を知りました。それを解決するための機能として、地方格差を補うリモート授業のサービス開発を思いついたことがそもそものきっかけです。新規事業として始まったのが2019年の秋で、立ち上がった当初は遠隔授業のニーズがこれほど早く高まるなどとは、まったく想像していませんでした。
当初は自社開発を考えていたのですが、突然コロナ禍がやってきてニーズが一気に大きくなり、スピードが重要になってきました。そこでパートナーを探した結果、EEOという中国のプラットフォーマーと協業することになりました。
──EEOは具体的にどのようなプラットフォームを展開しているのでしょうか?
酒井:教育版のWeb会議システムを想像してもらうとわかりやすいかもしれません。オンラインで先生と生徒の顔が見える状態でつながり、顔を見ながらホワイトボードが使えたり資料を表示できたりします。一般的なWeb会議システムは、資料を共有しようとすると全画面表示になり、相手の顔が見えなくなったり、顔と資料を同時に表示させるにはうまく配置しないといけなかったりしますよね。教える立場からすると、生徒の表情をうかがえることは非常に重要なのです。生徒の様子で理解度を判断しているためです。その点、EEOが提供するのは授業に特化したプラットフォームで、常に生徒の顔が表示されますし、そういった配置の作業も必要ありません。
我々はその「先生と生徒をつないで授業をおこなう」部分の技術を使い、さらに、授業前の準備や、授業後の録画提供、生徒個々人がどういう行動をしていたかという統計データを提供するなど、「準備段階からフォローまで」を用意することで、完結型のプラットフォームとして教育現場に提供することをやろうとしています。

オンライン授業画面UIイメージ(開発中)
──具体的にはいま、どういうフェーズなのでしょうか?
酒井:サービス導入は2021年4月の予定で、それに先駆けて、2020年10月から複数の教育機関と実証実験をスタートしました。実証実験でのフィードバックを活かして、より良い製品にしていきたいと考えています。
──EEOのプラットフォームを用いた開発のプロセスにおいて、気づきはありましたか?
酒井:中国と日本では、やはり感覚が違うなと感じました。中国は国土がとても広いので、教育格差は日本より深刻です。さらに、人口規模は日本とまるで異なります。「都心の先生が、地方の生徒たちにリモートで教えます」というところまでは一緒なのですが、中国の場合は集団授業になりがちです。先生1人につき30〜40人の生徒が授業を受けていて、一方通行の授業になってしまいます。
対して日本は、集団授業はどんどん減ってきていて、個別指導型の学習塾が増えてきています。そうするとニーズが異なってきます。EEOが提供するのは集団授業をメインにしたプラットフォームなので、日本のマーケットに即したチューニングが必要だと考えました。
──SGEDが提供する「完結型の授業プラットフォーム」の機能や特徴とは何ですか?
酒井:授業前の準備でいうと、例えば「誰がどの授業を受けますか?」といったことを、学習塾の先生たちは管理したいわけです。したがって、どの生徒がどの先生にアサインされているか、どんな授業を受けているのかをわかりやすく管理できる機能を開発しています。
また、特に重要な機能が教材の扱いです。お客様である学習塾のコアコンピタンスといえば、自社で作成している教材です。したがって、教材の流出は、大きなビジネスリスクなのです。オンラインだからといって「なんでもファイル共有して誰でもアクセスできる」ようにすることは避けたい。しかし、「授業に応じてコンテンツをフレキシブルに提供したい」というある意味相反した要求がある。そこを解決することがとても大事だと考えています。アップロードしたファイルに誰がアクセスできるのかを可視化したり、ある授業だけアクセスできるようにするなど、アクセス制御を実現することは、お客様のビジネスにとって重要で、こういったものを「授業前」機能として開発しています。
もうひとつは「授業後」の機能です。授業が終わった後に「この生徒は実際に授業を受けたのか」といった出欠管理や、「どれくらいアクティブに授業を受けたのか」といった情報をデータとして収集して解析し、「この子はこんな感じでした」といったようなデータとしてわかりやすく表示することを目指しています。学習塾の先生は、管理者や保護者に生徒の様子を報告する必要があります。この作業はとても大変なので、システムでサポートして簡略化することで教育指導などの本来集中したいところに時間を割けるよう手助けができればと考えています。

──今後は、どういう展開、どういうサービスにしていきたいとお考えですか?
酒井:ソニーの技術を積極的に使っていきたいと思っています。ソニーでは3R(リアリティ、リアルタイム、リモート)を重視していますが、リモート授業は現状、リアルな授業に比べて品質も満足度もまったく足りていません。それはつまり、まだまだ可能性があるということだと思います。例えばAIによる感情分析のような、リアルでは取り切れないデータを取ることなど、リアルを超えられる要素はたくさんあると思います。あるいは、ARで情報を重畳して提供することでさらに理解が進むこともあるでしょう。
テクノロジーの力でリアルを超えたサービスへと育っていけばいいと思っています。これらの技術は、技術要素としては出そろってきてはいるものの、それをどうやってサービスにしていくかは、まだまだ検討が必要だと思っています。技術とサービスの間にはどうしても乖離があります。しかも教育現場は、テクノロジーの面では改善の余地が大いにある領域です。そうしたなかで、テクノロジーを活用して、誰にでも使いやすいものを届けていくという我々のような活動が、ミドルウェアとして必要なのではないかと思います。ソニーは技術とUXを長きにわたり強みとしてきた企業ですから、技術とUXが結びついて、より良いサービスを創出できたらと考えています。
先生には効率化を、生徒には個別最適化を
──では次に、今川さんが携わっていらっしゃる「AIを活用した学びの実践研究」について教えてください。具体的にどのような活動なのでしょうか?
今川:「AIを活用した学びの実践研究」は昨年度から埼玉県が進めている実証事業で、AI技術を教育現場に活用していくことを目指しています。SGEDは事業者としてこの研究を受託し、ソニーコンピュータサイエンス研究所をはじめソニーグループ各社と連携しながら研究を進めています。この実践研究は、文部科学省が進めている「新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業」の1つでもあり、埼玉県の他に、岐阜県、京都府京都市、大阪府箕面市、香川県なども独自の取り組みをおこなっています。
具体的な研究内容について簡単にお話しできればと思います。埼玉県では毎年小学4年生から中学3年生までを対象に「埼玉県学力・学習状況調査」(以下、県学調)という調査を実施しています。毎年約30万人が対象となるので、埼玉県には膨大な教育データが蓄積されていることになります。埼玉県はこれまでにその膨大なデータをマクロ寄りの観点で分析し、政策に反映したり、現場にフィードバックしたり、ということをおこなってきました。一方で、子どもたち1人1人の視点にたったミクロな分析まではできておらず、いわゆる学びの個別最適化の実現が課題でした。そんななか、県学調に加え、学校に蓄積されている学習データも統合し、AI技術を用いてそれらのデータを分析することで子どもたち1人1人に合った学びを提供できるのではないか、ということで始まったのがこの研究事業です。

──今川さんはどのような役割を担われているのでしょうか?
今川:プロジェクトリーダーとしてこの事業に関わらせていただいていますが、主には先にお話しした「学校で蓄積されているデータ」を、現場の先生の負担をできるだけ抑えながら効率的に蓄積・分析するためのシステムを企画検討しています。県学調は、OECD教育・スキル局の局長も絶賛した調査で非常に優れたデータではあるのですが、年に1回の実施となるため、日々の学びでの個別最適化まで考えると頻度的な意味で物足りないというのが正直なところです。そのため、学校で実施されているテストや宿題といった時間的に細かい学習データもあわせて分析することが重要だと考えています。ただ、そうした学習データを分析しようとした際に直面することになるのが「いったいそれらのデータをどうやって取るのか?」という課題です。公立学校のICT環境の整備状況をみてみると整備が進んでいるとは言い難く、遅れている自治体が多いのが実情で、紙文化もまだまだ根強いです。とはいえ、日々の学習データを蓄積し分析しようとすると紙文化のままでは非常にハードルが高いわけです。そこでシステムを導入しようという話になります。先生の業務負荷は本当に大きな問題なので、どういうシステムを構築する必要があるのか、実証を通して先生の意見もいただきながらより良いものを提案していきたいですね。
データ分析に目を向けると、県学調の成績表をはじめ、子どもたちはさまざまなレポートをフィードバックとして受け取っています。しかし、それだけでは具体のアクションをおこせない子どもたちが多くいる、というも大きな課題です。内容をちゃんと読まずに捨ててしまう子どもたちもいるそうです。そのため「分析結果を起点に次は何をするとよいのか」つまり具体的なコンテンツまで提示する必要があると考えています。そうなると「データを蓄積し分析ができるようになるシステム」にとどまらず、「分析されたものから何をやればいいのかというコンテンツの提示」にまで包括的なインフラを提供していかなければならないと感じていて、その全体設計をどうするか模索しているのが現状です。
──いまはどういうフェーズなのでしょうか?
今川:この実践研究は4カ年の計画になるのですが今年はその2年目になります。昨年は埼玉県からいただいた県学調のデータを分析し、分析手法の検討と分析をもとにしたアドバイスのプロトタイプを作成しました。今年は、プロトタイプのブラッシュアップに加え、分析結果を踏まえた具体的なコンテンツの検討やテストデータなどの学校データの活用検討を進めていくフェーズになります。また、学習データ以外にどのようなデータを活用すればより役に立つフィードバックを提供できるのかについても検討を始めていくことになると思います。テスト結果などの学習データはとても有益な情報であることはもちろんなのですが、個別最適化を目指す上で見落としているデータもあるはずです。例えばそれが生活習慣や知能タイプに関するデータだとすると、そうしたデータもあわせて分析することで、例えば「朝型のタイプで、慎重に物事を考えるタイプの子どもには、こういう学びが向いている」といったフィードバックもできるのではないかと思っています。最終的には、正誤情報にとどまらない、より個に即した学びの機会を実現したいですね。
──文科省がICTを学びの場に活用したい理由はどこにあるのでしょうか?
今川:プログラミングや探究学習などこれからの時代に必要といわれている新しい学びを提供していくことや、データを活用して学習の個別最適化を図り誰一人取り残すことのない公正な学びを実現することなどが狙いだと思います。後者の個別最適化は私たちの実践研究でも目指しているところですし、公教育という観点ではとても重要なことですね。ただ先生方とのコミュニケーションを通して感じたことは、「取り残されそうな」子どもたちに対してはさまざまな工夫をこらしてサポートする一方で、いわゆる成績上位や中位の子どもたちにはそこまでのサポートができていないのではないかということです。もちろん子ども数十人に対して先生は1人なので限界はありますが、できるできないにかかわらず1人1人が可能性を広げていける、そんな学びの場を目指していくことが真に公正という意味でも必要だと思いますし、それができて初めて全体の底上げが実現できるのではないかと思います。

──そうした課題があるなかで、具体的にどのようにしてAIを活用されていこうとしているのでしょうか?
今川:学習データを分析して、それぞれの子どもたちがどこでつまずいているか、何が得意なのか、つまり現在地を明らかにし、それを踏まえてつまずきを解消するためのコンテンツや得意なことをさらに伸ばすためのコンテンツをレコメンドする、というのがまずひとつあります。先生目線で考えれば宿題の作成やマル付けが大変なので、その日の授業の理解度に応じた宿題が自動調整・自動アサインされ、かつ先生は翌朝システムにログインすれば宿題の取り組み状況などが把握でき、それに基づいて授業の組み立てができるようになる、といったこともやっていきたいですね。
また、夏休みのような長期休暇の宿題を考えるとき、例えば「2時間くらいでできて、数学の図形の問題を」と設定すると子どもたちの習熟度に応じて問題集が生成され、それを個別にアサインしていくといったことも可能です。そうなると、先生の負担が減るのはもちろん、子どもたち1人1人に合った課題を出すことが可能になりますし、先生は生じた時間で授業研究やデータに基づく子どもたち1人1人のサポートにより多くの時間を割くことができるようになります。
──夏休みの終わりのほうになって焦りだし、「みんなで集まってやろう」となっても、「あれ、みんな課題が違うね」ということになるわけですね。
今川:はい、そのイメージです。ただここで問題になってくるのが子どもと保護者、それぞれからクレームがくるケースです。子どもからすれば「自分だけ問題が違うのがイヤ」というパターン、保護者からすれば「なんでウチの子だけ」といったパターンです。現状でも実際におこっているクレームですね。もちろんその気持ちはわからなくもないのですが、1人1人に応じたサポートをしようという立場にたつとむしろ違って当たり前で、そこはマインドを変えてもらえるよう根気強く向き合っていくしかないかなとも思っています。
──確かに、親の意識改革も大切ですね。
今川:はい。現状は主に子どもたちと先生にフィードバックを提供することを想定していますが、保護者に対しても子どもの様子をよりこまやかに知ることができる、など有益なフィードバックを提供していく必要があるのではという議論がすでにチーム内で出ています。いまは、通知表を見るか子どもから聞くかぐらいだと思うのですが、通知表に記載できる情報はどうしても限られてしまうため、例えば親もシステムにアクセスできるようにして、学習状況や学校での様子を確認できるようにすることで、保護者の意識改革や子どもとのさらなるコミュニケーションにつなげていけたら良いのではないかと考えています。子どもにしてみるとあまり見てほしくないのかもしれませんが。
──プライバシーの観点から壁を感じたりしますか?
今川:当初から想定はしていましたが、セキュリティとプライバシーの問題は想像以上に乗り越えないといけない壁が高いですね。要求基準を満たすセキュリティ環境をどう構築するか、「仮名化」など個人情報のリスクをどう軽減するかなど、システム設計は困難なものになると感じていますが、連携しているグループ各社の協力も仰ぎながら解決策を導き出していきたいです。セキュリティ担保の一方で子どもたちにログインしてもらうことを考えると複雑なログインIDやパスワードを覚えてもらうことは難しいですし、「わたしのパスワードこれだから」と友達に見せてしまうといったことがおこりうるため、それらも想定しながら、使いやすさと安全の担保を総合的に考えなければなりません。

──今後は、ソニーらしいツイストの効いたゲーミフィケーション的な要素も取り入れたりしていく予定なのでしょうか。
今川:入れたいですね。ただし、今回の実践研究でそこまで到達することは難しいかもしれない、というのが本音です。この実践研究は、将来的な事業化を目指していますので、事業化フェーズにおいては、ソニーらしいコンテンツも取り入れていきたいと考えています。
個人的な思いですが、学びにおいて4つ、パーソナライズしたいものがあるのです。「何を学ぶか」、「どうやって学ぶか」、「いつ学ぶか」、「どこで学ぶか」です。いま私たちが進めているプロジェクトでは、「何を学ぶか」と「どうやって学ぶか」の一部をパーソナライズできると考えています。しかし、「どこで」と「いつ」の実現はなかなか難しいため、酒井さんが進められているオンライン授業プラットフォームと将来的には合流することでいつ、どこで、何を、どうやって、を自由に組み替えられるような、新しい教育の「場」を提供できると考えていますし、そこにソニーらしいコンテンツが加わることで新たな感動体験を創り出せるのではないかと考えています。




