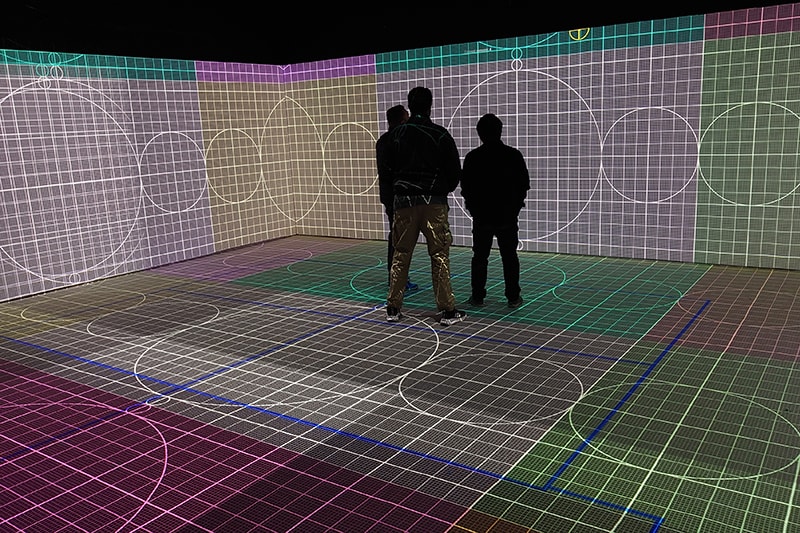Collaboration
医療分野に打ち込んだ大いなる一手
『ORBEYE(オーブアイ)』※ が生まれるまで
2019年3月29日

脳神経外科や脊椎・整形外科など外科手術において、微細な組織の拡大観察は精緻な処理を可能にし、手術の安全性や有効性に直結する。そこで大きな役割を果たしているのが手術用顕微鏡だ。
そんな手術用顕微鏡だが、これまで主流だった光学式は、接眼レンズを(場合によっては) 長時間覗くことになるため、術者に不自然な姿勢を強要し、疲労をもたらす一因となっていた。さらに手術室にいる他のスタッフが手術部位で行われている事をリアルタイムで把握しづらいため、予備動作やとっさの対応が取りづらいといった課題も内包していた。
そうした手術用顕微鏡システムに新たな概念をもたらしたのが、『ORBEYE』である。ソニー株式会社が持つ4Kおよび3D映像技術と、オリンパス株式会社の医療領域におけるノウハウが融合した、従来とはまったく異なるシステムだ。
ソニーから出向し、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社の一員として、メカ設計や電気設計、レンズユニットの開発に携わった3名に、その経緯を訊いた。
プロフィール
-

深谷 浩司
ソニー・オリンパスメディカル
ソリューションズ株式会社
イメージング開発2部 -

加戸 正隆
ソニー・オリンパスメディカル
ソリューションズ株式会社
イメージング開発2部 -

鎌田 祥行
ソニー・オリンパスメディカル
ソリューションズ株式会社
イメージング開発2部
実感は、後からやって来る
──みなさんはそれぞれ、『ORBEYE』の開発に際してどのような役割を担ったのでしょうか?
鎌田:私は主にメカ設計を担当しました。
加戸:レンズの開発に携わりました。光学であったり、レンズのメカであったり、その制御の部分などの担当です。
深谷:私は、電気設計やシステムまわりを担当していました。
──医療用製品の設計に携わるということで、ソニー株式会社(以下、ソニー)においてコンスーマー製品を設計していた時と比べると、やはり「心の持ちよう」は違ったのでしょうか?
深谷:「電気回路の設計をする」という意味では、やることはあまり変わりません。ですが、適合させなければいけない規格や、故障した時にどう振る舞わなければいけない、といったリスクマネジメントの部分では大きな違いがありました。最初は、単純にやることが増えて大変だなという印象でしたが、実際に『ORBEYE』が使われている医療現場を見学させてもらった時に、徹底したリスクマネジメントが不可欠であることを実感し、そこから意識が変わりました。

加戸:私も、徐々に意識が変わっていきました。最初の頃は「どんな製品を作るべきなのか」を何もないところから考える日々だったので、とにかく開発に必死でした。『ORBEYE』が臨床の現場に持ち込まれ、実際の手術に用いられる、という場面に立ち会わせていただいたのですが、自分の作ってきた製品が、患者さんの命を救うために使われていることを目の当たりにし、やっていることの重要性を改めて意識しました。
──開発過程で病院の先生のところに話を聞きに行ったりしたのでしょうか?
加戸:『ORBEYE』は、元々オリンパス株式会社(以下、オリンパス)の方である程度温めていた製品で、HD(High Definition)のプロトタイプも存在しました。ですのでソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社(以下、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ)としてスタートした時点では、先生のところへリサーチに行くことはせず、まずはプロトタイプのブラッシュアップから取り掛かりました。
Joint Venture(以下、JV)として一緒にやっていこうとしているなかで、我々が加わることでどういった価値が出せるか、例えばオリンパスで考えていたプロトタイプのカメラひとつを取っても、どうレベルアップさせていくかを深く考えていく必要がありました。そこで「机上評価」をとにかく行ったんです。例えば、会議室で模型を先生に見てもらい、話を聞き、そのなかでできるだけ先生の言葉をつかまえて咀嚼し、真のVOC(Voice of Customer:顧客要望)が何かを考え、理解して、仕様面に落とし込んでいく……という作業を、可能な限り何度も繰り返しました。

深谷:医療機器の場合、コンスーマー向けの製品と違って自分がユーザーではないわけです。つまり、自分のなかで機能や性能や仕様を確定できないんです。最終的に使っていただく先生方にフィードバックをいただかないと、果たして製品として妥当なものなのか判断ができません。ですので、先生方には繰り返しご意見をいただきながら、ブラッシュアップしていきました。
できたものを模擬的に使っていただき、「これなら信頼して手術に臨めるね」と言っていただいた時は嬉しかったですね。
鎌田:私も、先生からのフィードバックでいちばん印象に残っているのは、はじめて4K 3Dの映像を先生にお見せしたタイミングでした。まだ開発初期でプロダクトの形状もまとまっておらず、テーブルいっぱいに機材が並んでいるような状態だったのですが、先生は大感激してくださいました。その時、これでVOCを満たせるのではないかと思いましたね。
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ以前にオリンパスで技術検討されていた製品は、画質面でまだ問題があると言われていたそうなので、我々がこの製品に携わった意義、そしてこの製品の価値を、あのタイミングではじめて感じたことを覚えています。
「ソニーの技術」が貢献したのは?
──オリンパスが温めていた「土台」に対して、具体的にソニーのどのような技術が加わることで、『ORBEYE』は完成したのでしょうか?
深谷:この製品には、照明を当てるというところから、イメージャーで画像を撮り、それを転送し、画像処理をして、最後モニターに出すというところに至るまで、ソニーのデジタルイメージング技術が集積しています。
例えば4Kで撮った後にどう処理するか、という点でいうと、医療機器ですので、4K 3Dという膨大なデータを、いかに早く処理してモニターに出すかが鍵となります。手元とモニターの間でタイムラグがあると、当然手術に影響を及ぼしてしまいますので、そこをいかに短くできるかが重要なポイントとなるわけです。
映像処理という観点でいうと、処理をすればするほど画質の改善はできます。ただ、それをすると時間がかかります。ですので、いわゆる協調設計、高画質にするためにどれだけの映像処理を行うか、また光学の部分でどこまで画質を確保するのかといったバランスを考慮しながら、全体として手術に最適な製品となるよう作り上げていったイメージです。
加戸:『ORBEYE』の至上命題のひとつに小型化がありました。従来の手術用顕微鏡は、光学式ということもあり、とても大きなものでした。ソニー・オリンパスメディカルソリューションズでは、コンスーマー製品で小型化のノウハウがあったソニーからの出向者が光学設計も担当することで、光学系をグッと小さくすることに成功しています。
『ORBEYE』はカウンターバランス方式のアームで構成されているので、光学系の大きさで顕微鏡の大きさが決まり、この製品でいうと、そこからアームの大きさや本体の大きさが決まっていったので、小型化するには光学系を小さくすることが必須条件だったんです。その点でも、ソニーの技術が貢献したのではないかと思います。

医療機器ならではの苦労、JVならではの苦労
──完成に至るまで、いちばん苦労をしたところを教えてください。
鎌田:このプロジェクトは5年くらいかかりましたので、いろいろあります。苦労の塊というか、ここまで苦労したのははじめてでした。以前の部署では、短期間で、ライフサイクルに合わせてコンスーマー製品を作っていましたから、また違った苦労でした。
まず、メカ設計で苦労したのは重さです。これまで自分が携わってきた製品は、重くても2kgくらい、軽い場合は100gくらいでしたが、『ORBEYE』は約200kgで、重いものだと1部品が20kgくらいあり、自重で曲がってしまう部品もありました。自重による変形なんて、小さな製品であれば考える必要はありません。そういったことも含めて、メカ設計者として根底から意識を変えさせられました。大きなサイズ感や、それにまつわる操作性といった部分を改善していくところが、とにかく難しかったですね。
あとは、JVならではの苦労もありました。
医療機器の場合、出荷責任は全部工場が持つことになります。この製品は、我々以外に、ソニーとオリンパスそれぞれの製造事業所や、販売を手がけるオリンパスが携わるわけですから、出荷前の評価ひとつとっても、まったく違う文化の中で連携する必要がありました。お互いの考えを正しくやり取りするのにはとても苦労しました。
深谷:確かに、ソニーとオリンパスという異なる企業文化のなかで、しかも医療機器というソニーとしてはまったくノウハウがない分野に挑んだわけなので、オリンパスやオリンパスからの出向者の方々にいろいろ教えていただきながら開発を進めました。そうやって密に情報交換をしながらやっていくところが、プロジェクトとしてのチャレンジだったかなと思います。
加戸:それでいうと、私はレンズの開発に携わっていたのですが、ソニーのメンバーとのやりとりに苦労がありました。
設計をする際には、背景であったり、どこへ向かえばいいのか、といったゴールや目的を示し、それを設計者間で共有する必要があるのですが、今回の場合は、ソニーがこれまで作ったことのない医療機器ということもあり、私たちが作ろうとしている製品が、何をするもので、誰がどういうふうに使うものかということが伝わりにくく、そのため、製品の仕様としてこういうものを作りたいんだ……という共通理解を得ることに、当初苦慮しました。
私自身、医療に精通しているわけではなかったので、学びながら、それをすぐ人に伝えなければいけないのは一苦労でしたね。
ネクストステップへの思い
──『ORBEYE』が無事世に送り出されたところですが、みなさんは既に次を見据えているのでしょうか?
深谷:やれることはまだたくさんあると思っています。ORBEYEを改善していくことはもちろん、違う形の提案もいろいろできると思っています。イメージング機器ですので、多くの画像情報を手術現場から取得、加工して、いかに先生方にとって有益な画像情報として提示することができるかが肝だと思っています。その点に関しても、まだまだソニーのイメージングやセンシングの技術を使って向上していけると考えています。
あとは、いかに快適に使っていただくかというユーザビリティの観点からも、まだまだ突き詰められると思っています。それがひいては患者さんのためになるわけですから、おろそかにすることはできません。
鎌田:今回の1号機で、従来の顕微鏡とは異なる形での提案ができました。これまでの手術室における常識を覆すような、新しい価値の提案ができたのではないかと思っています。例えば、接眼レンズを覗く動作がディスプレイを見る動作になったことで覗く動作をせずに複数人で使用することができることは新しい価値のひとつです。実際に好意的なフィードバックもいただいています。ただ、まだまだやりきれていなかったところはたくさんありますし、ソニーの中で眠っているいろいろな技術は、もっともっとたくさんあります。それを使うことによって、いまある形が最適なのかという問いを立て直し、もう一度検証していきたいと考えています。
今回は、最初にあった土台を元にこれが「最適」だと考え作りましたが、入れる技術によって「最適」とは何かが変わってくるのではと思っています。医療機器の分野は開発スパンが長いので、5年後、10年後を見据え、その時点で出てくるであろう技術を視野に入れながら開発に取り組みたいと思います。

加戸:『ORBEYE』の仕様が固まるまでの過程では、開発時のリソースなどを理由に、いろいろと諦めた機能がありました。鎌田さんがおっしゃったように、ソニーのなかにはいろいろな技術があり、光学系やセンサーや信号処理といった分野でも、私たちが知らないようなネタが山のようにあります。そうした技術を使って、どういう医療のニーズに応えていけるのか、またどういった改善が求められているのかということを、一生懸命考えているところです。
そのニーズを掘り起こすためにも、臨床評価をしていただいている先生から、いろいろなコメントをいただいているところです。先生方は、的確なコメントを残してくださいますが、さらに我々は、その言葉の裏に隠れた真のニーズというものをきちんと読み解かなければならないし、浮かび上がったニーズと、ソニーが持つ技術をきちんとつなぎ合わせて製品化していくことも、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズの価値だと考えています。
──ちなみに、『ORBEYE』に対するフィードバックとして、どのような声があったのでしょうか?
加戸:『ORBEYE』は、モニターで患部を見ることができますし、同じ画像を手術室にいる人たちが共有できるので、教育的なメリットもあるという声をいただきました。
深谷:あと、看護師の方々に好評なんです。いままでは、接眼レンズを覗き込むタイプのため、手術をするメインの先生と助手の先生しか直接画像を見ることができず、周りのスタッフの方は、ビデオで撮影しているものをモニター越しに見ていましたが、画質的には物足りなかったわけです。それがORBEYEでは、先生が見ているものとまったく同じものが見られるということで、手術の状況を把握しやすく、やるべきことが予測できるというところで、動きやすいという声をいただきました。
鎌田:従来と比べて、アームを動かせる範囲が広い点も、非常に好評でした。実際に先生がアームを自由に動かしているのを見て、術式によって、動かし方や患部チェックの方法が多様に存在することに気が付きました。ニーズは掴んでいたつもりでしたが、それ以上に先生方にはやりたいことがたくさんあるんだなと。

ソニーが医療分野に踏み込んだ意義
──医療においてUX(User Experience)という言葉は軽いのかもしれませんが、例えばAR(Augmented Reality)や人工知能といった技術が加わることで、手術のやり方自体も変えていける可能性はあるのでしょうか?
加戸:夢としては持っています。『ORBEYE』によって、ソニーは手術室の中心に入ることできたわけですから、これを核として、いろいろな機器の連携はもちろん、手術室自体を変えていきたいと思っています。そうやって手術の現場の仕組み自体を変えていくためには、単純にスタンドアローンで2号機、3号機……と作っていくのではない、さまざまな可能性を探っていく必要があると考えています。
個人的には、ARや人工知能にしても、単純に『ORBEYE』の後継機種ではなく、ステップを3つくらい飛び越えたところ、これは、「ソニー・オリンパスメディカルソリューションズだからこその着眼点とものづくりだね」という製品を提案できればいいなと思っています。
──医療分野においてそうした新しい提案をしていくにあたり、新たにメンバーを迎えるとするならば、どのようなスキルやマインドセットを持った人材を求めますか?
鎌田:一緒に働く上では、いろいろなことにどんどん興味を持っていける人に来ていただきたいです。別にいまそういう人がいない、というわけではなくて(笑)。なぜかというと、ソニーには数多くのいろいろな技術が転がっています。一方で、医療の現場にもニーズは大量にあるのですが、見えづらいというか隠れて存在しています。興味を持って自分からどんどん行かないと、どちらもなかなか掘り出せないと感じます。ですので興味を失わない人が、この業界には必要かなと思います。
深谷:同じような話になりますが、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズはいろいろなことができるんです。設計だから設計だけをやっていなさいというわけではなく、現場に行ってリサーチやインタビューをしたり、技術的には研究者の方々と話をしたりといった形で、いろいろな場面があるので、そうした広いフィールドで自ら動いて活躍していただけるような人材がいいかなと思います。
会社としても、さまざまな部署から人材で構成されているのでダイバーシティがあります。それを楽しく感じられる人が、実際来られたとしても、楽しく仕事ができるのではないでしょうか。
加戸:ぜひ、いろいろな人に来ていただきたいです。ソニー・オリンパスメディカルソリューションズでの開発には、多様な視点が必要ですので。あとはお二人が言ったとおりですが、これだけ幅広く自由に「あれがやりたい」「これがやりたい」と言える環境ってあまりないと思います。自分のキャリアの積み上げ方についていろいろ聞いてくれる土壌が、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズにはあるんです。
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社:
ソニー株式会社のイメージング技術とオリンパス株式会社の光学技術・医療事業のノウハウを活かし、4K 3D外科イメージング事業を目的として設立。2013年より外科医療機器の開発に着手し、2015年に4K外科手術用内視鏡システムを、2017年には4K 3D手術用顕微鏡システム(ORBEYE)をそれぞれオリンパスから上市した。
ソニーグループにおけるメディカル事業の取り組み:
1980年代からソニーが培った映像技術などを生かしたプリンター、カメラ、レコーダー、モニターなど様々な医療用映像機器を開発。また、免疫・がん・再生医療の研究などに適した細胞分析装置も提供している。そして、より高精細な映像で精度の高い手術を実現したいという医療の現場の声に応え、4Kの医療用映像機器を、記録、伝送、再生までトータルで提案。さらに、オリンパス株式会社、ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社とも連携し、4K 3D手術用顕微鏡システムの製品化※を実現するなど、ソニーグループとしてメディカル領域に取り組んでいる。
※:製造販売元(モニター、レコーダーは除く):オリンパスメディカルシステムズ株式会社、モニターおよびレコーダーの製造元:ソニー株式会社