
『Sony Design:
MAKING MODERN』
京都展
トークカンファレンス
秋の京都で開催した『Sony Design: MAKING MODERN』展では、ソニーデザインを代表する、2015年の最新プロダクトやプロトタイプなどの近作と、
春の銀座展で好評だった歴代モデルのデザインを3日間限定で展示。2日目にあたる11月28日には、ソニーのデザイナー6人によるトークカンファレンスを行ないました。
「人のやらないことをやる」ソニーのチャレンジ精神を体現するソニーデザインとは何か。6人がそれぞれの思いを語り、
参加者のみなさんとともに明日のデザインについて考えたカンファレンスの模様をお届けします。

センター長
さまざまなデザイン領域での幅広い経験を経て2014年からセンター長。

エンターテインメントロボット「QRIO」のデザインなどを担当。

ディレクター
オーディオカテゴリー製品全般のアートディレクションを担当。

ディレクター
ホームカテゴリー製品、R&D系プロジェクト全般のアートディレクションを担当。

ディレクター
コーポレートタイプフェイスの開発を起案するなど、コミュニケーション領域全般のアートディレクションを担当。

ディレクター
新規事業領域のデザインを手掛け、現在はスマートフォンなどのアートディレクションを担当。

6人のデザイナーたちによる
プレゼンテーション
事前登録の人数が当初の想定を大きく超えたため、会場を同キャンパス内の大きなギャラリーへと変更して開催したトークカンファレンス。当日参加の来場者も多く、開演前から会場は熱気に包まれた状態に。
この日、登壇したのはクリエイティブセンターのセンター長をはじめとする6人のデザイナー。20分ずつという限られた時間でしたが、それぞれが関わるプロジェクトやプロダクトを例にあげながら、ソニーデザインの今やこれからについて凝縮したプレゼンテーションを行いました。
徹底してディスカッションする
「デザイン審議」を通して培われてきた
ソニーデザイン
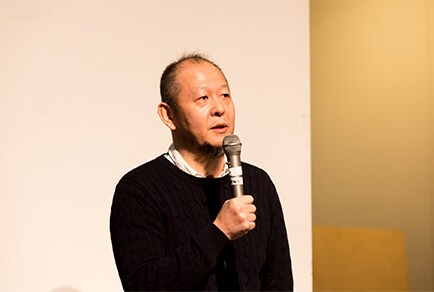

まず最初に、トークカンファレンス全体のガイダンスを兼ねてソニーデザインの考えについて話したのは、ソニーデザインを率いるクリエイティブセンターセンター長の長谷川豊。
来年、創立70周年を迎えるソニーの歴史において、世の中にないものを生み出すソニーのイノベーション精神は常に語られてきましたが、そこには必ずテクノロジーとデザインの融合、ハーモナイズがあると長谷川は言います。そのデザインの根底にある、遊び心や冒険心、五感の気持ちよさなどを示した上で、どのようにソニーデザインとしての共通認識を保ってきたかについて語りました。
長谷川:我々に特徴的なアプローチだと思いますが、「デザイン審議」という場を必ず設け、商品カテゴリーや専門領域を越えて、デザイナーの間であらゆることを徹底してディスカッションしています。ソニーの海外デザイナーにも英語で「Shingi」と言えば通じるほど。「審議」を通して認識を深め、我々の中に暗黙知として培われてきたものをとても大事にしています。
また、エレクトロニクスに留まらない、「ソニー銀行」や昨年より営業開始した「ソニー不動産」のような新しい事例も紹介しながら、一つひとつのプロダクトはもちろん、ショップやイベント展開まで、トータルで世界観を構成するデザインアプローチの重要性について説明し、話を締めくくりました。
長谷川:どんな新しい事業領域になっても、「次の原型を作るCreating New Standard」ということを追い求めていきたい。そうした様々なチャレンジをみなさんにも見ていただいて、いいも悪いもダイレクトに意見をいただければと思います。
これからのロボットデザインは、
「Motion(動き)」と
「Interaction
(人との対話)」


二足歩行のエンターテインメントロボット「QRIO」のデザインを担った沢井邦仁は、そのロボットデザインのプロセスを丁寧に紹介。その上で、これからのロボットデザインに必要な要素として、「Motion」と「Interaction」の2点をあげました。Motionを追求したロボット「QRIO」に対して、これから問われるのはInteraction、人との対話であると言います。完璧な自然対話ができるロボットを今すぐに開発することは難しいかもしれませんが、「デザインの力でそう感じさせることはできます」として、Smart Bluetooth® Speaker「BSP60」のデモ映像を披露しました。
沢井:道具をユーザーが操作して、より便利な状況を生むのではなく、ユーザーは何もしないで、ただ「頼む」ことで同じ結果が得られること。これを「Concierge Interface」と名づけて、デザインに活用できないかと考えています。BSP60のデモ映像の中にも、電話をかけてと頼むと、すぐに電話をつないでくれる場面がありましたが、まさにこのようなところにこれからのロボットデザインの可能性があるのではないでしょうか。
余白を美しく見せる
デザイン哲学


オーディオ全般のアートディレクションを手がけている詫摩智朗の話は、11月に発売したばかりのハイレゾ対応ヘッドホン「h.ear™」と、その背景にある多様性、アイデンティティー創出について。h.earは、上質な音を楽しむことを知っているけれども、マニアックではない志向性を持った層に向けて、メカニカルな印象を押しつけることなく、極力シンプルなデザインで着こなしができるプロダクトとして開発。その世界観の鍵となるCMF(カラー / マテリアル / フィニッシュ)として、ヘッドホンに使われるあらゆる部材、パッケージ、ショップフロントまで、「Single color finish」と「Color in between」、単色使いと中間色で貫徹するために、千を超えるトライというこだわりぬいた色合せを重ねてきたことを紹介。その上で、多様性と独自性を持ったソニーのオーディオ製品に共通するデザイン言語として、「Negative Space(余白)」の概念について説明しました。
詫摩:不必要なオブジェクトは減らし、残った本質的な要素を凝縮してシンプルな塊にまとめます。構成する要素が一つの塊に収まって同じ質感になったとき、それぞれのオブジェクト自体ではなく、オブジェクトとオブジェクトの間に美しい「余白=Negative Space」が結果的に生まれてきます。これが我々のテーマになっています。
こうした共通デザイン言語の存在が、ブランディングだけではなく、開発チームやユーザーとのコミュニケーションを円滑にするメリットを生み出すことにもつながっています。
居住空間の中で、
家電はどうあるべきか?


田幸宏崇が携わる「Life Space UX」シリーズは、居住空間の中でエレクトロニクスはどうあるべきか、その基本概念を再定義して、暮らしに寄り添うようなコンセプトから生まれた商品群。その開発にあたって、商品ごとの「Context=文脈、前後関係、背景、状況」を考え、拡張することでデザインを作ってきたことを説明。
田幸:たとえば、「Life Space UX」の4K超短焦点プロジェクター「LSPX-W1S」は、「建築と家具の間」のプロダクトとして位置づけられます。そして、そのコンテクストを「壁の前に置かれる / 147インチの大画面の下 / 写真のような4Kの高精細画像」という言葉で表現。そこから「舞台・ステージ」といったイメージを得て、意図的に水平に広がりを持たせた形や、舞台の幕が上がるように天板がせり上がってプロジェクター部が開口される機構が生まれました。
他にも、LED電球スピーカー「LSPX-100E26J」、ポータブル超短焦点プロジェクター(2016年春発売予定、地域未定)、シンフォニックライトスピーカー(2016年春発売予定、地域未定)についても、それぞれのコンテクストを説明。居住空間に寄り添う「Life Space UX」で考えられてきたコンテクスチュアルなデザインを語りました。
最後は、ポータブル超短焦点プロジェクターとシンフォニックライトスピーカーを実際に使ってみせながら、「クリエイターやユーザーの方々に自由に使い方を考えてもらえるような、新しいプラットフォームになることを大事にしています」とデモンストレーションを終えました。

ソニーオリジナルフォント「SST®」は、
必然によって生まれた


福原寛重が紹介したのは、今年、ソニーのコーポレートタイプフェイスとなった、オリジナルフォント「SST」。エンターテインメント、金融など幅広い事業領域を持ち、世界中でビジネスを展開するソニーが、同じ書体で、同じようにメッセージを伝えるために「SST」は計画され、その最初の段階から93言語に対応させることを目指しました。これは、ソニーがビジネス展開をしているほとんどの国をカバーできる数です。タイプフェイスの開発は、書体の制作で長い歴史を持ち、Helvetica®やFrutiger®のライセンスを所有するモノタイプ社と共同で進められ、Helveticaのような硬質さ、Frutigerのような読みやすさ、その両方を兼ね備えたフォントとしてデザインされています。
福原:コミュニケーションデザインにおいては、ぱっと見てメッセージがひと目でわかること、なんとなくいいよねということが伝わることが大事だと考えています。そしてもうひとつ、何ごとも期初から100%にするというのは不可能に近いと思っています。もしそれができるのであれば、もう誰かがとっくにやっているはず。1%ずつ積み重ねていくことで、その先に100%を目指したい。
トークの冒頭で、「なぜSSTフォントを作ったのか? それはあったほうがいいから。もしソニーにオリジナルのフォントがあるならと考え、想像してみると、やっぱりあったほうがいい。そう信じこんでいくことが大事」と言った福原は、最後にも「志」の大切さを強調して話を終えました。
新規事業創出プログラムで、
活発に行なわれる新製品開発


最後に登壇した石井大輔は、2014年にスタートしたソニーの新規事業創出プログラム「Seed Acceleration Program(以下、SAP)」を紹介。本社ビルの1階につくられた「Creative Lounge」を共創スペースとして活用しながら、事業オーディションを行い、選ばれた提案チームがそのリーダーを中心として、さまざまなトライアルを繰り返しながら商品化を目指すという、これまでの製品開発とはまったく違ったプロセスでプロダクトが生まれています。そのプロセスにおいて、デザインの力は不可欠。デザイナーも含めた小さなチームで、UIやブランディングなどアイデアを具現化するためのトライを重ねています。
その事例として、クラウドファンディングで目標額の10倍以上の支援を集めたウェアラブルデバイス「wena wrist」や、石井自身がデザインを担当した、アプリと連動するスマートDIYキット「MESH™」が紹介されました。「MESH」のデザインにあたっては、いきなり手を動かすのではなく、ワークショップやディスカッションを社内外で積み重ねることで、アイデアを絞り込んでいきました。
石井:まずは生まれた商品アイデアに対してユーザートライアルを繰り返すことで、その本質を探り当てます。それから、インダストリアルデザイン、コミュニケーションデザイン、ユーザーインターフェイスデザインが一体となってデザインを進めたところで、ふたたびユーザートライアルを経て、商品化へ。このような次につなげていくためのトライアル、そのたびごとの気づきが重要だと考えています。
最後は6人全員が壇上に上がって、会場からの質問に答えました。質問の多くは「ソニーらしさ」を問うような内容で、壇上のデザイナーと会場のお客さまが一緒になって、ソニーデザインやこれからのデザインについて考えを深めていくような時間となりました。
石井:無駄をなくして、目的や本質が何であるかを考え、そぎ落としていくのが一番ソニーらしい答えだと思います。カセットテープのサイズに限りなく近づけたウォークマンのように。そういったミニマムな定義をしていくことがソニーのブランドにつながるのでは。
詫摩:商品が出るたびに、デザイナー同士が一切の遠慮をせずに議論を繰り返す「デザイン審議」が、やはりソニーに特有のやり方かなと思います。そこでの徹底的な議論によって、暗黙知と呼ばれる共通認識ができているように思います。
「今ふと思ったんですけど」と、話しはじめたのは田幸。
田幸:ソニーらしさを定義付けようとしたり、ガイドラインをつくったりというのは、いつもやっています。だけど、「ソニーらしさって何?」と言われているうちが華なんじゃないかなと。ソニーの外側にいる方たちがソニーらしさを感じてくれるのだったら、それが一番いいなって思いました。
質疑応答もすべて終えた後、進行役で今回のイベントの総合プロデュースを行ったクリエイティブセンタープロデューサーの市川和男がこのように話して、この日のトークカンファレンスを締めくくりました。
市川:ソニーのようにエンターテインメントから金融事業まで持っている会社は、実は世界でもあまり例がありません。我々は、そうした全体を見通しながらデザインをやっています。我々もまだ、進化していくソニーのソニーらしさを探し続けているというのが答えなのかもしれません。


SST is a trademark of Monotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
Helvetica and Frutiger are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
